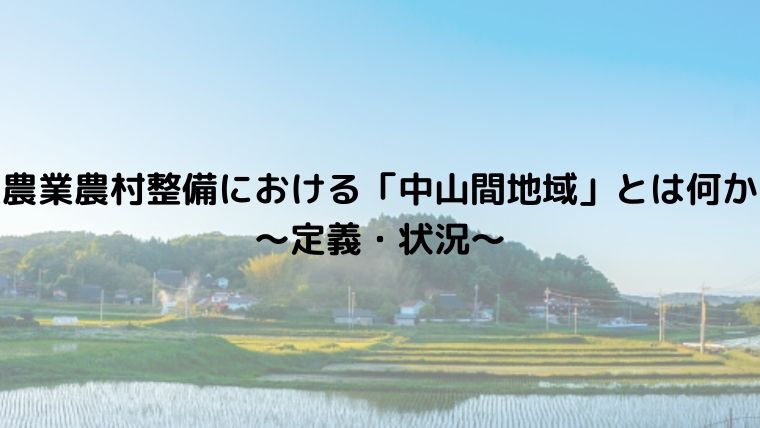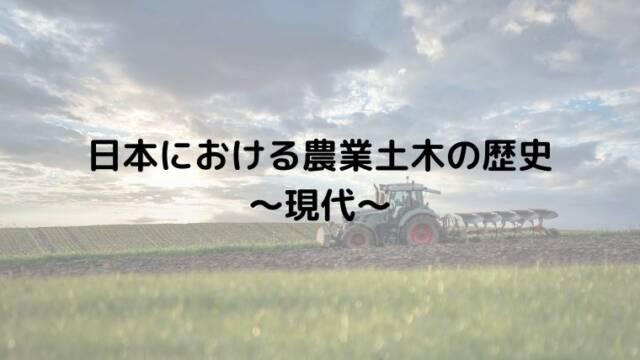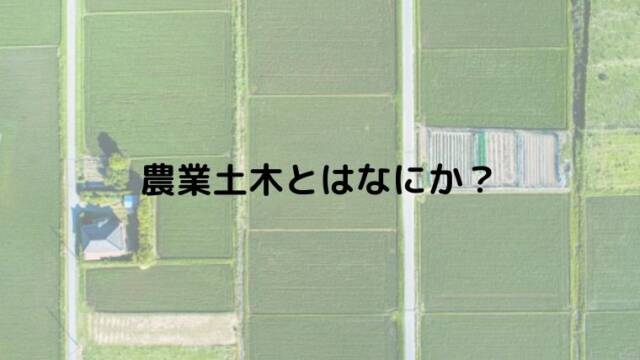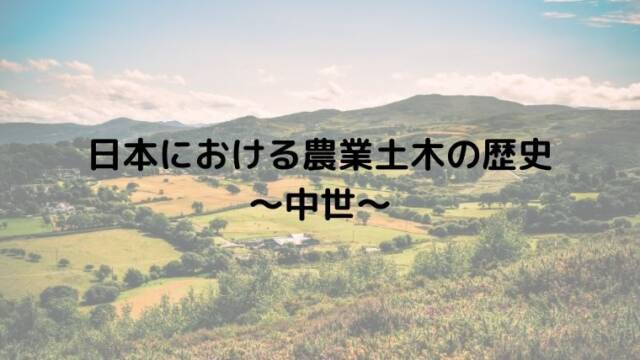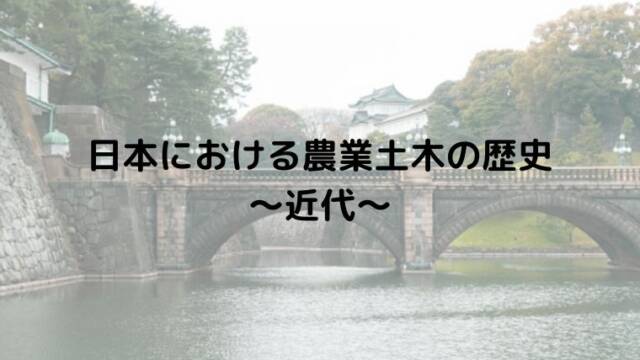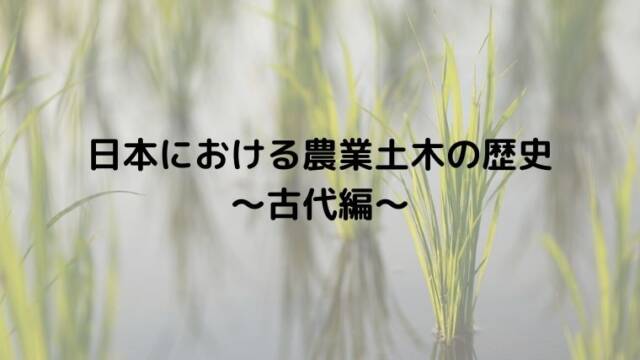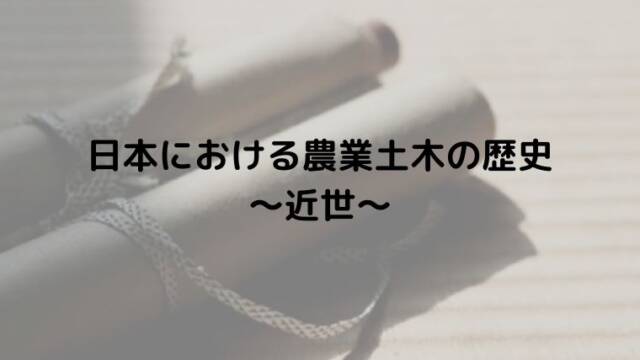中山間地域は、国土面積の約7割を占め、中山間地域の耕地率は8.4%と低いながら、耕地面積38.2%・総農家人口44.6%・農業産出額の40%を占めるなど、農業において重要なポジションです。
しかしながら、平地地域と比べると、農業生産における条件不利・過疎化や高齢化による担い手不足・生活環境整備の遅れなどの問題が残っています。
そのため、農業農村整備では、中山間地域の農業生産基盤・農村生活環境基盤の整備をすることで、農業・農村の活性化を図る「中山間地域総合整備事業」を実施しています。
ここで取り扱われている「中山間地域」の定義・状況についてまとめてみます。
目次
中山間地域の定義

中山間地域の定義については、以下の2通りが考えられます。
- 農林統計に用いられる農業地域類型における「中山間地域」
- 食料・農業・農村基本法や中山間地域等直接支払制度における「中山間地域等」
上を狭義の中山間地域、下を広義の中山間地域とも表現されることもあります。
農林統計に用いられる農業地域類型における「中山間地域」
農林統計における農業地域類型区分では、都市的地域・平地農業地域・中間農業地域・山間農業地域の4地域類型を設定しています。
中山間地域とは、農林統計における農業地域類型区分のうち、中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域のことを指します。
各農業地域類型については、以下の表をご覧ください。
| 農業地域類型 | 基準指標 |
| 都市的地域 | 可住地に占めるDID面積が5%以上で、人口密度500人/㎢以上又はDID人口2万人以上の市区町村及び旧市区町村。 可住地に占める宅地等率が60%以上で、人口密度500人/㎢以上の市区町村及び旧市区町村。ただし、林野率80%以上のものは除く。 |
| 平地農業地域 | 耕地率20%以上かつ林野率50%未満の市区町村及び旧市区町村。ただし、傾斜20分の1以上の田と傾斜8度以上の畑との合計面積の割合が90%以上のものを除く。 耕地率20%以上かつ林野率50%以上で、傾斜20分の1以上の田と傾斜8度以上の畑の合計面積の割合が10%未満の市区町村及び旧市区町村。 |
| 中間農業地域 | 耕地率が20%未満で、都市的地域及び山間農業地域以外の市区町村及び旧市区町村。 耕地率が20%以上で、都市的地域及び平地農業地域以外の市区町村及び旧市区町村。 |
| 山間農業地域 | 林野率80%以上かつ耕地率10%未満の市区町村及び旧市区町村。 |
食料・農業・農村基本法や中山間地域等直接支払制度における「中山間地域等」
食料・農業・農村基本法の第35条では、「山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域」のことを「中山間地域等」と定義しています。
中山間地域等とは、中山間地域等直接支払交付金の対象地域である、地域振興立法9法で定められた地域又都道府県知事が指定する特認地域のことです。
地域振興立法9法とは、 以下の9法を指します。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
- 山村振興法
- 過疎地域自立促進特別措置法
- 半島振興法
- 離島振興法
- 沖縄振興特別措置法
- 奄美群島振興開発特別措置法
- 小笠原諸島振興開発特別措置法
- 棚田地域振興法
地域振興立法9法対象地域・特認地域についての詳しい内容は以下の表をご覧ください。
| 特定農山村法による 「特定農山村地域」 | ・下記の1~3の要件すべてを満たした市町村。また、市町村単位で2満たし、かつ旧市町村単位で1・3を満たすことで旧町村単位で地域指定。
|
| 山村振興法による 「振興山村」 | 下記の1~3の要件すべてを満たした市町村(旧市町村単位)
|
| 過疎地域活性化特別措置法による 「過疎地域」 | 下記の人口要件・財政要件を満たす市町村 要件1
【財政力要件】 要件2(基準年の見直しにともなう激変緩和措置)
【財政力要件】 |
| 半島振興法による 「半島振興対策実施地域」 | 三方が海に囲まれ、一方が本土とつながっている陸地部分とからなる地域であって、下記の3要件に該当する地域(半島振興対策実施地域)
|
| 離島振興法による 「離島振興対策実施地域」 | 下記のいずれかの要件を満たす地域全部又は一部
|
| 沖縄振興特別措置法による 「沖縄」 | 沖縄県 |
| 奄美群島振興開発特別措置法による 「奄美群島」 | 奄美群島(鹿児島県奄美市・大島郡の区域) |
| 小笠原諸島振興開発特別措置法による 「小笠原諸島」 | 小笠原諸島 ・孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島・西之島・火山列島を含む) ・沖の鳥島 ・南鳥島 |
| 棚田地域振興法による 「指定棚田地域」 | 勾配が20分の1以上の棚田が1ha以上ある地域で下記のいずれかの要件に該当するもの地域(旧市町村単位)
|
| 特認地域 | 都道府県知事が地域の実態に応じて指定した自然的・経済的・社会的条件が不利な地域「特認地域」 |
中山間地域の現状

食料・農業・農村基本法の第35条の2において、「国は、中山間地域等においては、適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うこと等により、多面的機能の確保を特に図るための施策を講ずるものとする。」としています。
中山間地域はどのような生産条件の不利があり、それがどう補正されているか、以下の事項についてまとめてみます。
- 農地の状況
- 経営規模の状況
- 労働人口の状況
農地の状況
田面積に占める傾斜1/100以上の割合は、平地地域で約4割のところ中山間地域では約8割です。
整備率も低く、田の区画整備率は約5割、畑の灌漑整備は約1割となっています。
山林が近いため鳥獣害の被害にも遭いやすく、年間の農作物被害額約200億円の多くは中山間で発生しています。
そのため、耕作放棄地面積は中山間地域で約5割が発生しています。
農地の利用状況・農業生産基盤の整備状況の詳細について、下記記事でまとめていますのでご参照ください。
経営規模の状況
傾斜地が多いため、田1枚の面積が小さく、農地集約・集積がしずらい点があります。
中山間地域では経営規模1ha未満の農家が約7割、1戸あたり経営耕地面積は約1.1haとスケールメリットがありません。
そのためか、農業就業者1人あたりの農業所得は平地地位と比べ約40万円ほど低いです。
労働人口の状況
中山間地域は1集落あたりの土地面積は広いが、総農家数・耕地面積は平野地域より小さいです。
中山間地域の高齢化率は約3割で、全国に比べて約10年以上先をいく水準で高齢化が進行しています。
インフラの整備も遅れており、DID地区までの所要時間が長いなど、生活環境の整備が必須になっています。
まとめ

農業農村整備における「中山間地域」の定義・状況についてまとめました。
「のうぎょうとぼく」の中では、農業土木に関する豊富な記事を書いています。
農業土木について勉強できる本については下記にてまとめていますので、ぜひご覧ください。
参考ページ:農業土木の勉強におすすめな参考書・問題集を紹介!