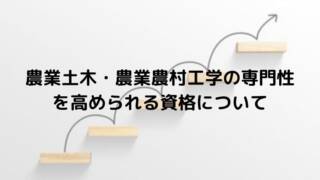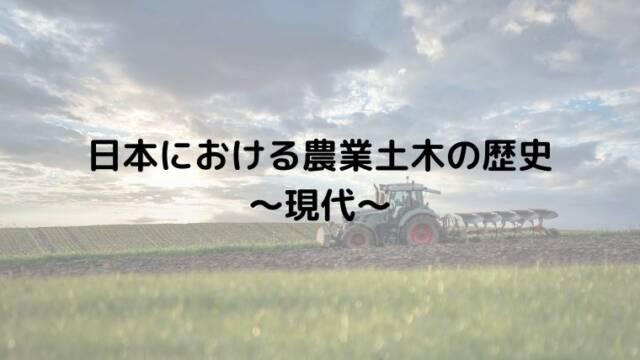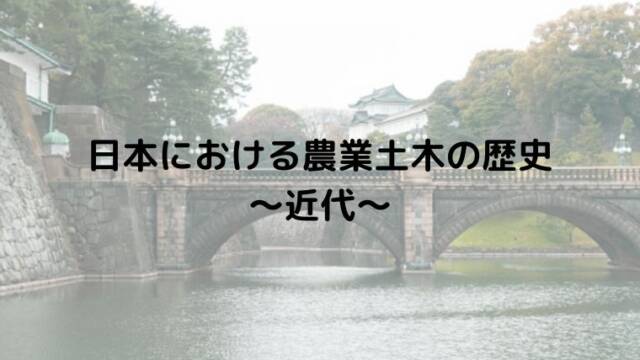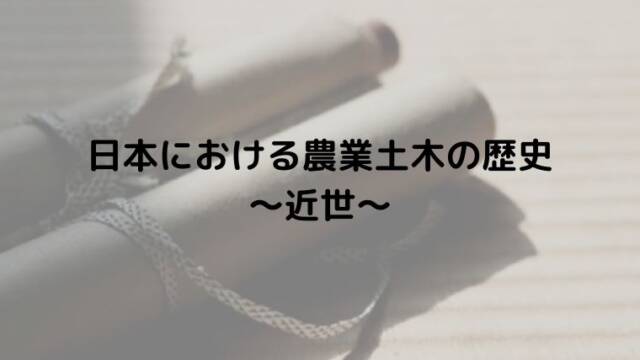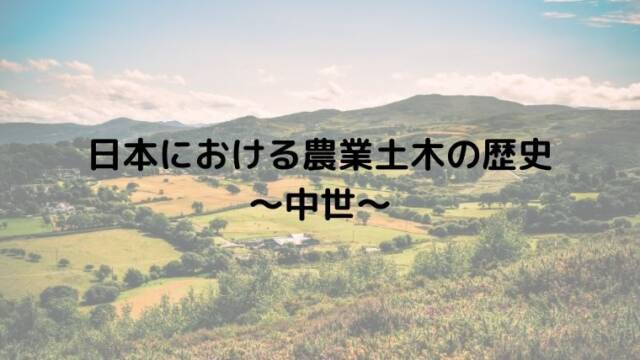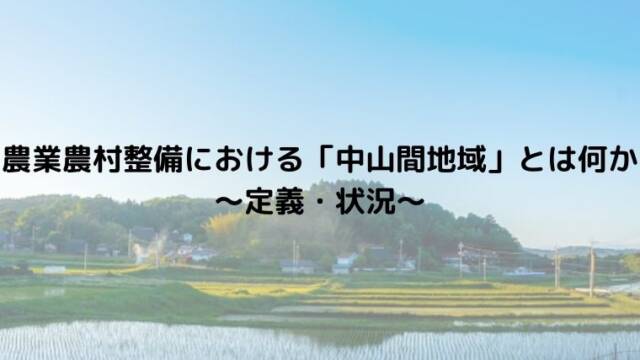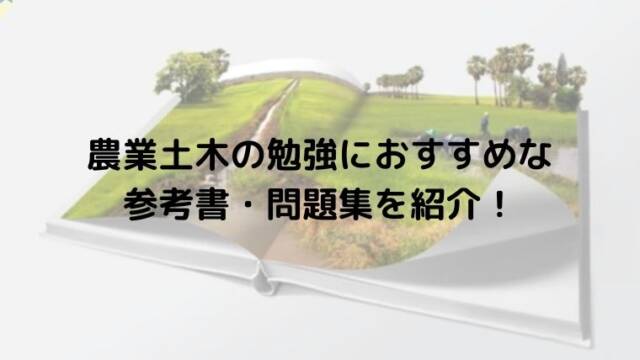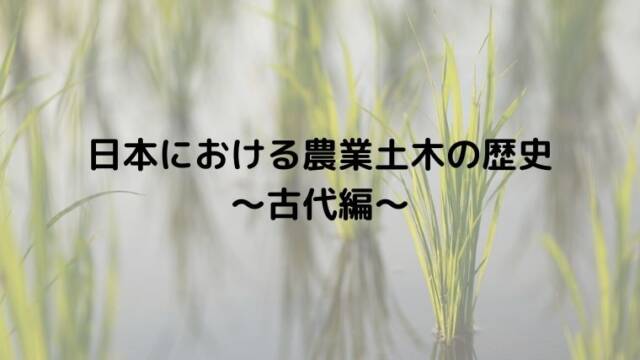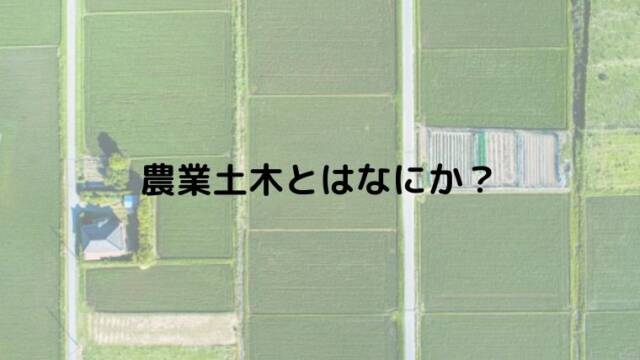農業土木とは農業に関する土木分野で、土木技術によって「農地の生産性の向上・農家の労働力低減」を図ります。
日本では、水田農業が軸となり社会基盤が形成された背景で、農業と土木が密接になりました。
独自の技術として発展した農業土木についてまとめます。
農業土木とは

農業土木は、農業の生産力向上・農村の生活水準向上などに資するために、多岐にわたる事業があります。
農業土木の工事内容としては以下のものが挙げられます。
- 圃場整備
- かんがい排水施設整備
- 農道整備
- 農地防災整備
- 中山間地域総合整備、農村振興総合整備
など幅広い知識が必要になります。

農業土木と近い呼称

農業土木に似た呼称として、「土地改良」「農業農村整備」「農業農村工学」などがあります。
- 土地改良:農用地・用排水路等の基盤整備のみ
- 農業農村整備:農村振興整備も含む
- 農業農村工学:農地集積などのソフト面も含む
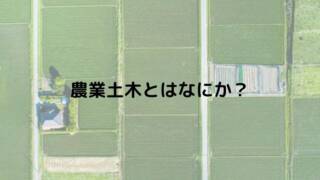
農業土木の歴史について
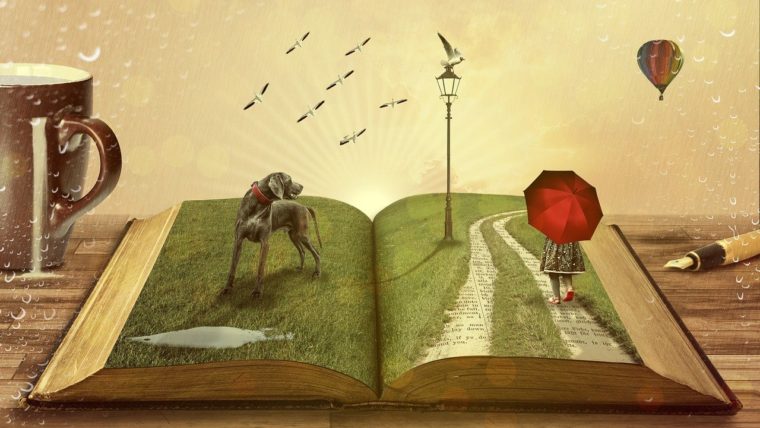
農業土木は、自然に存在する土・水を、農業に効率的に利用できるように発達した土木技術です。
日本の発展の礎となる技術で、日本の歴史に大きく関わっています。
農業土木の技術進歩の遍歴を確認するため、
- 古代
- 中世
- 近世
- 近代
- 現代
にわけてまとめてみました。
古代
日本では、縄文時代後・晩期には中国伝来の水田稲作が行われていた可能性が高いとされています。
弥生時代以降に水田稲作が本格的に始まり、北九州から本州北部へ、日本各地へ急速に広がっていきます。
口分田を与えるために区画整理が行われ、土地の単位として条理制も導入されます。
制度だけではなく、農業の基盤を整える農業土木の技術も整備されます。
行基・空海などが技術者として、中国の最新の土木工事をを民衆広げていきました。
土木事業の社会事業化を朝廷に認められるようになり、豪族からの資本提供も受け、農業土木事業が形作られます。
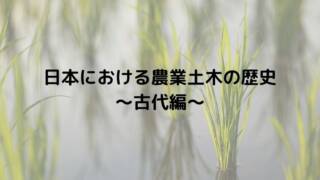
中世
723年に3代まで開墾した土地の所有を認められるようになる「三世一身法」が制定されました。
しかし、私有期間が切れてしまう最後の代では土地を取り上げられてしまうため、農地が手入れされずに荒田に戻る問題が発生しました。
そのため、開墾した土地は永年で所有できる「墾田永年私財法」が743年に制定され、開墾する意欲も活発になることで、農業土木の技術も発達していきます。
公家・寺社・武家など支配層による活発な開墾による大規模な私有農園(荘園)が力をつけ、荘園単位の水田開発は進みます。
次第に巨大になっていく荘園領主同士の土地争いや税を盗む盗賊対策などのため、農民が傭兵とし、これが武士の始まりになります。
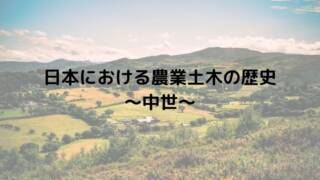
近世
戦国大名の台頭により、荘園単位の小さな水利開発から、域規模での大きな利水・治水の開発が行われました。
戦国大名は年貢を賦課するために、領地の水田・畑を調査(検地)を行なっていましたが、土地の等級・単位の基準すら統一されておらず、豊臣秀吉が関わった1582年から1591年に実施された「太閤検地」によって大きく是正されます。
江戸時代には、関東郡代伊奈忠次による「関東流」・紀伊藩井沢弥惣兵衛為永による「紀州流」の技術によって、治水技術が飛躍し、現在の治水技術の礎になっています。
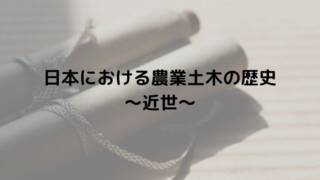
近代
明治政府は、全国の土地について統一的な基準で全ての地籍を把握し、その土地に税を課すため、1873年に地租改正を実施しました。
地租改正について長期的な視点では2点良いことがあります。
- 地租が一定であるため、収穫を増やすことで農民の手取りが増えること。
- 金納であるため、栽培する農作物が自由になったこと
このため、反収の増加に資するための高収益作物導入・土地生産性の向上のための農地造成が実施される起点になります。
明治政府による中央集権的な施策の結果、国営で大規模な開発事業が実施されるようになりました。
安積疏水・明治用水・北海道開拓など、数千〜万haの受益面積を持つ大きな農業土木工事が施工されています。
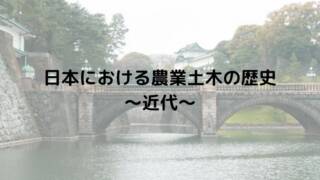
現代
戦後の復興にあたって、農業土木の開墾・開拓・灌漑排水の技術が総動員されました。
農業土木事業は、農産物の生産力を増強するためだけの技術から、防災設備・公共施設整備が実施される農村振興の根幹をなす総合開発事業へと変貌します。
1949年に土地改良法が制定されたことも契機になり、国営での土地改良事業が大きく加速することになります。
農業の近代化・合理化によって、昭和40年代には米の完全自給が達成されます。
しかし、1952年には栄養改善法が施行されて米偏重の是正が叫ばれ、食の欧米化も進み、米の余剰が発生しました。
そのため、新規の開田禁止・政府米買入限度・自主流通米制度の導入・米の生産調整を1970年に開始しました。
1999年に農業基本法が「食糧・農業・農村基本法」に変わり、食糧の安定供給の確保と農業・農村のもつ公益的・多面的な機能の発揮が掲げられました。
多面的機能として、以下の5つの機能があります。
- 国土の保全
- 水源の涵養
- 自然環境の保全
- 良好的な景観の形成
- 地方文化の伝承
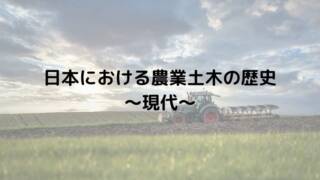
まとめ
農業土木の概論についてまとめました。
勉強に使用した本をこちらでまとめさせていただいております。
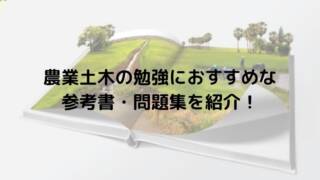
農業土木の知識をより深く学びたい場合は、以下の資格を取得することで身につけることができますので、紹介させていただきます。