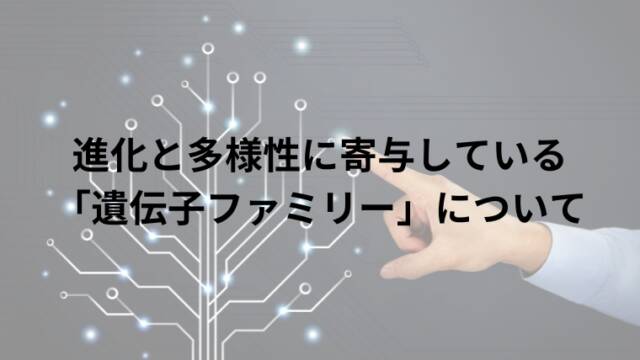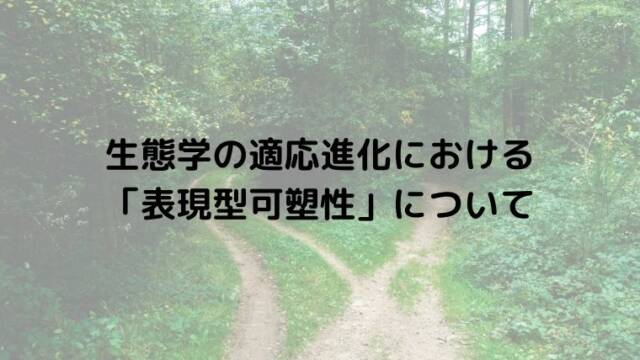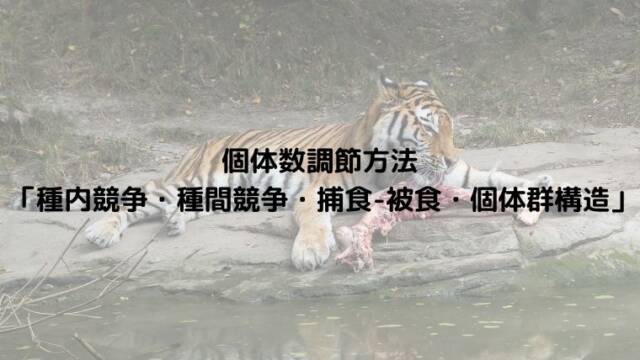生態学において、生物が持っている生活史をどのように理解するかが重要になります。
HOWという生理学視点である至近要因・WHYという進化的視点である究極要因から見ていくことができます。
今回は、進化的視点の要である「進化とは何か」をまとめます。
目次
進化の定義

集団が祖先から受け継いだ対立遺伝子の全てを集めたものを「遺伝子プール(gene pool)」と呼びます。
進化とは遺伝子プールの構造が次世代において変化することです。
そのことにより祖先とは異なる形態・生活史・生息場所を持つことが現れます。
生物学上の進化では優劣などの価値基準を含まないので、退化に思われる変化も遺伝子プールの構造が変化しただけであり、進化として捉えられます。
種分化が起こる前の遺伝子プールの構造変化を小進化、種分化以上が起きた遺伝子プールの構造変化を大進化と区別されることがあります。
種分化については以下のページでまとめてありますので、ご参照ください。
参考ページ:生態学における「種分化」の種類について
主な進化理論
進化理論として、総合説と中立説があります。
総合説は、突然変異と自然選択を中心に考え、集団遺伝学・古生物学などの多くの分野を総合しています。
中立説は、突然変異と遺伝的浮動と安定化選択に基づいて考えられ、DNA塩基配列・アミノ酸配列の置き換わりに適用されるので、「分子進化の中立説」とも言われます。
進化の要因
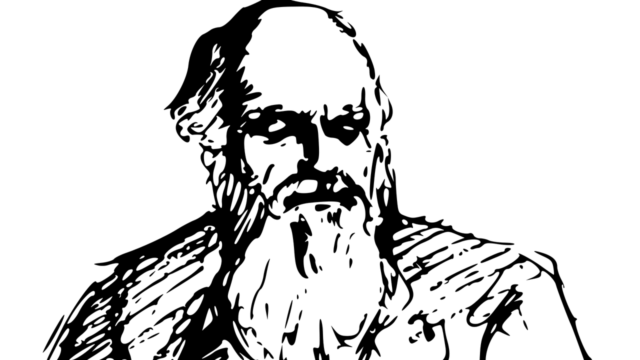
遺伝子型の頻度が、対立遺伝子がランダムに出会う確率と等しい状態を、ハーディ・ワインバーグ平衡(Hardy-Weinberg’s equilibria)と呼び、この平衡が崩れると遺伝子プールの構造変化が起きます。
平衡を崩して進化の要因を生み出すのは以下の事象などです。
【進化を導く要因】
- 突然変異(mutation)
- 自然選択・自然淘汰(natural selection)
- 遺伝的浮動(genetic drift)
- 遺伝子流動(gene flow)
ハーディ・ワインバーグ平衡(Hardy-Weinberg’s equilibria)
| pA | p‘a | |
| pA | p2AA | pp‘Aa |
| p‘a | pp‘Aa | p‘2aa |
個体群内に対立遺伝子Aとaがあり、A遺伝子の遺伝子頻度をp、a遺伝子の遺伝子頻度をp’すると、p+p’=1となります。
この個体群が作る次世代の個体群の遺伝子型の比は AA:Aa:aa=p2:2pp’:p’2 となる
Aaのホモ接合体は全てAを持ち、Aaのヘテロ接合体ではその半分がAを持ちます。
次世代のAの頻度qは、q=p2+1/2×2pp‘=p2+p(1ーp)=p
よって、次世代でもAの頻度はpは変わらず、遺伝子頻度は永遠に変化しません。
これを「ハーディ・ワインバーグ平衡」「ハーディ・ワインバーグ法則」と呼ばれ、成立するためには、以下の条件を全て満たしている必要がある。
- 突然変異がない
- 性選択がない
- 遺伝的浮動がない
- 遺伝子流動がない
- 遺伝子型や表現型の違いによる自然選択がない。
逆にこれらの条件を満たさなければ、遺伝子頻度が変化します。
進化を導く要因①突然変異(mutation)

突然変異(mutation)には、紫外線・放射線・有害物質などにより、遺伝子(DNA)に起こる遺伝子突然変異、染色体に起こる染色体突然変異があります。
変異が必ずしも常に表現型に変化が現れるわけではありません。
表現型に変異を起こす物理的・化学的な要因は変異原(ミュータゲン)、表現型に変異が生じた細胞・個体を突然変異体(ミュータント)と呼びます。
体細胞突然変異は次世代に伝わることはないが、生殖細胞突然変異は次世代に伝わり進化に寄与します。
遺伝子突然変異
遺伝子突然変異は、DNA複製の際の転写ミス・DNA損傷などによって、DNAを構成する塩基に種々の変化が生じることで起きます。
- 点突然変異:1個のヌクレオチドの置換・欠損・挿入の変異
- ミスセンス突然変異:コドン内の塩基の変化・置換により、異常タンパク質が作られる突然変異
- ナンセンス突然変異:アミノ酸のコドンを終止コドンにして、転写されたメッセンジャー RNAの翻訳が完了しないままに終了してしまい、異常タンパク質が作られる突然変異
- フレームシフト突然変異:塩基の挿入・欠失によってオープンリーディングフレームがずれてしまう突然変異
染色体突然変異
染色体突然変異は染色体異常と呼ばれ、数量的変化と形態的変化があります。
【数量的変化】
- 倍数性:染色体数がゲノムのセットとして倍加
- 異数性:数本の染色体が増減した
【形態的変化】
- 欠失:染色体の一部が消失
- 重複:繰り返しが発生
- 転座:2本の染色体がそれぞれ切断してつなぎ変わり
- 逆位:染色体が2か所で切断して、その中間部分が逆になって再結合
- 切断:染色体の一部が切れる
進化を導く要因②自然選択・自然淘汰(natural selection)

自然選択・自然淘汰(natural selection)とは、生存・繁殖において有利に作用するものは保存され、有利でないものは除去され、遺伝的変異が選択されることです。
一般に生物の繁殖力が環境収容力を超えて同種内で限られた資源(食料、配偶者)を奪い合う競争が起きるため、生存・繁殖に有利な個体はその性質を多くの子孫に伝え、不利な性質を持った個体の子供は少なくなります。
そのため、生存・繁殖に有利な形質が自然選択の効果が長い間蓄積され、次第に生物が変化して新しい種が生じます。
自然選択は以下の3つの条件を満たされれば必ず作動し、自律的に進みます。
- 変異:同種内において様々な形質が個体間で現れること
- 遺伝:次世代に変異が遺伝すること
- 選択:その変異が原因となって繁殖・生存に個体差が生じること
自然選択の例として、「ダーウィン・フィンチ、キリン・オオシモフリエダシャク・キイロショウジョウバエ」が挙げられることが多いです。
自然選択を以下のように分類することができます。
- 純化淘汰(安定化選択):遺伝子プールにあたらに生じた変異遺伝子・組み型を取り除くように選択される
- 方向性選択:新しい環境に適した遺伝子の適応度が高くなり、新しい表現型の個体が選択される
- 分断化選択:集団内で大きく異なる表現型が適応度の面で有利となり、中間型の適応度が低くなり、生殖隔離が起こるほどの分化が進むように選択される
- 頻度依存選択:生殖・生存の有利さが、相手がどのように振る舞うかに依存しており、遺伝子型の頻度に選択される
自然選択を測るための「遺伝率」については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。
参考ページ:自然選択を測るための「遺伝率」について
進化を導く要因③遺伝的浮動(genetic drift)

遺伝的浮動(genetic drift)とは、集団の繁殖個体数が無限ではないため、世代を超えて偶然に生じる遺伝子頻度です。
無数に交配できればメンデルの法則が成つが、子が少なかったり個体数が少ない場合に成り立つことはほとんどありませn。
極端な場合には、対立遺伝子のどれかが子孫に伝わらないことも起こり得て、これをボトルネック効果と呼ばれます。
少数の個体が集団から離れた場合、ボトルネック効果が働いて、新しい集団の遺伝的変異が一挙に減少する「創始者効果(founder effect)」が現れます。
進化を導く要因④移住・遺伝子流動(gene flow)

遺伝子流動(gene flow)とは、ある集団から別の集団への遺伝子の移動のことで、遺伝子プールを融合させることにより遺伝的分化を成立させない働きです。
動物が集団間を移動したり花粉が種間で動いたりする時、集団中の対立遺伝子頻度を変化させます。
1個体が高い移動性を持つほど、移住のポテンシャルは高くなります。
逆に遺伝子流動が止まるような状態になると、集団間の分断が発生し、種分化につながります。
まとめ

進化の定義・要因についてまとめました。
生態学についてより深く勉強するのに、おすすめの書籍をまとめていますのでご参照ください。