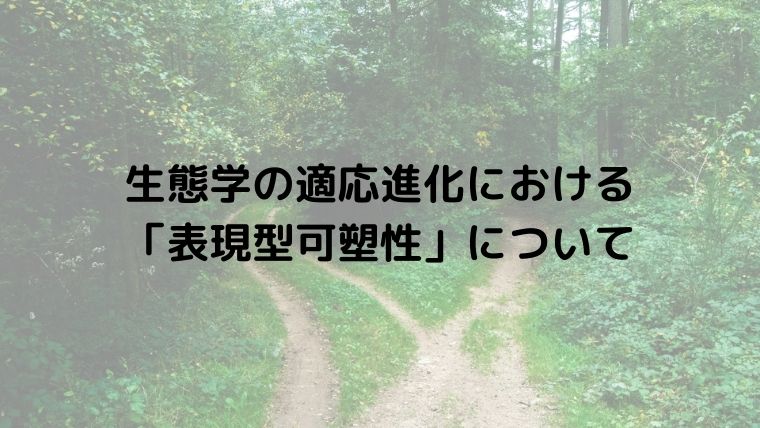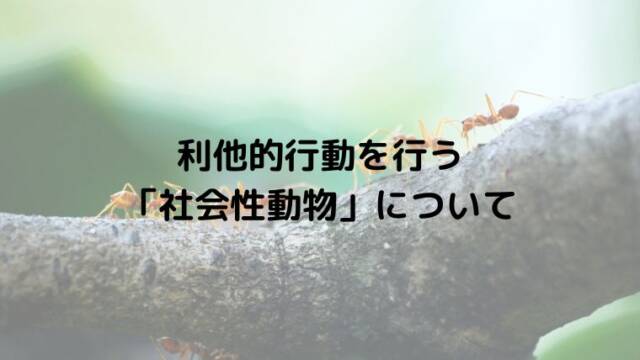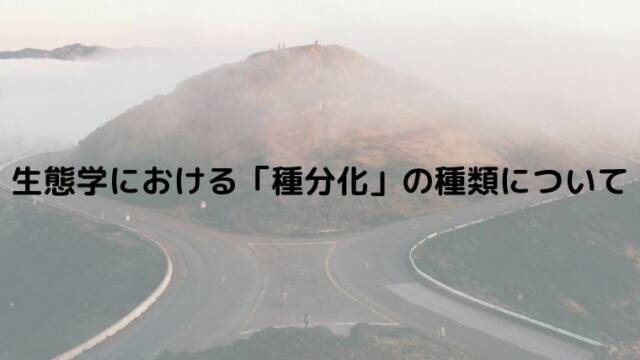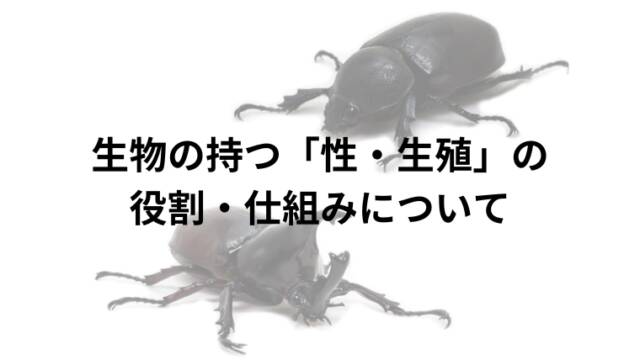自然選択が長く働き続けると、生物の適応度が最大化し、生物の形質は環境に最も適応したものに進化します。
同じ遺伝子でも、表現型を変えることができる「表現型可塑性」を持つこともあります。
今回は、この「表現型可塑性」についてまとめます。
表現型可塑性(phenotypic plasticity)とは?

同じ遺伝子型の個体が、発現する表現型を環境によって変化させられることを「表現的可塑性(phenotypic plasticity)」といいます。
環境の変化などの環境シグナル「合図(cue)」を生物が感知することができる場合、個体成長の段階で形態・生活史の特性を変化させることがあります。
どちらの表現型も発現できる能力を持っていて、環境条件によって都合の良い表現型を発現します。
環境の変化に対する形質の量的な反応を反応基準といい、魚が食物が少ない時に繁殖を早めて死亡して繁殖そのものができなくなる危険性を減らします。
環境に適応する表現的可塑性による形質変化は、適応進化による変化幅よりも小さく、適応的表現型可塑性ともいいます。
環境の影響として、「餌・捕食者・同種同体」が挙げられます。
表現型可塑性の例

表現型可塑性の例として以下の3つを挙げます。
【表現型可塑性の例】
- トビバッタ
- ミジンコ
- ウキシバ
表現型可塑性の例①:トビバッタ

トビバッタは、生息密度が環境シグナル「合図(cue)」になり、表現型可塑性が発現します。
通常の低密度下に生息する場合、「孤独相」と呼ばれ、体色が隠蔽色で比較的無害です。
しかし、高密度下になった場合、「群生相」と呼ばれ、以下のように変化し個体数を爆発的に増やしながら大移動を行います。
- 体色が黄色・黒色に変化
- 長距離飛翔に適した形態に変化
- 1卵鞘あたりの卵数が少なくなるが、卵自体が大型に変化
アフリカに生息する「サバクトビバッタ」は、農作物を含むあらゆる植物を根こそぎ食い荒らすことで知られています。
表現型可塑性の例②:ミジンコ

ミジンコは、捕食者から放出される「カイロモン(受容者側が利益を得る他感物質)」が環境シグナル「合図(cue)」になり、表現型可塑性が発現します。
フサカ幼生の放出する匂い物質を感受すると、後頭部にネックティースと呼ばれるトゲ状の防御形態を形成することで、通常の個体より捕食率が低くなることが知られています。
もっとも狙われやすい中型ミジンコたちが、もっとも防衛(表現型可塑性を発現)することが最新の研究から判明していました(Nagano, M., Sakamoto, M., Chang, K. H., & Doi, H. (2023). Predator‐induced plasticity in relation to prey body size: A meta‐analysis of Daphnia experiments. Freshwater Biology, 68(8), 1293-1302.)。
表現型可塑性の例③:ウキシバ

ウキシバには、水位が環境シグナル「合図(cue)」になり、表現型可塑性が発現します。
抽水性と浮葉性があり、それぞれの環境に適した性質に変わります。
水位が低い場合、根を張れるので葉が斜め上に向かって伸びる抽水性が現れます。
水位が高い場合、茎や葉が水面に浮きながらランナーのようにはって伸びる浮葉型が現れます。
まとめ

生態学の適応進化における「表現型可塑性」についてまとめました。
生態学についてより深く勉強するのに、おすすめの書籍をまとめていますのでご参照ください。