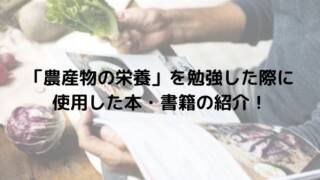食材の栄養素は料理の仕方次第で大きく変化します。
栄養を大きく損なう調理をしてしまうと、食材の栄養素を活かすことができません。
逆にちょっとした工夫・要点を知るだけで、効率的に栄養を活かすことができます。
今回は、「ニンニク」の栄養・効能を活かす効果的な料理法をまとめます。
ニンニクの主な栄養・効能

【ニンニクの注目成分】
- ビタミンB6:1.5mg
- 葉酸:92μg
- カリウム:510mg
- リン:160mg
【ニンニク 生100gあたり成分 七訂日本食品標準成分表より】
ニンニクは原産地は西アジア地中海沿岸で、滋養強壮の効果が高い食材です。
古代エジプトのピラミッド建設に従事した人たちが毎日食べていたとも言われているほど、古くから使用されています。
「黒にんにく」が通常のニンニク熟成したもので、健康成分である「ポリフェノール」や「S-アリルシステイン」が増加し、糖度が上昇して甘みが増します。
栄養素以外に注目すべき成分として硫化アリル(アリイン)が挙げられます。
硫化アリル(アリイン)
ニンニクに含まれる硫化アリル(アリイン)は、硫黄化合物でスルホキシドに分類されるファイトケミカルです。
アリインはアリナーゼという酵素によって分解され、アリシンが生じます。
アリシンには血液を固まりにくくするので血栓の生成を抑え、血液サラサラ効果があります。
また、消化液の分泌を助けて食欲を増進する作用をはじめ、新陳代謝・神経の沈静化に必要なビタミンB1の吸収と活性化を促す作用があり、疲労回復効果もあります。
大量に摂取するとヘモグロビンが減少し、過度に摂取すると赤血球破壊・血圧低下・嘔吐・腸内菌破壊の症状が出るので、食べ過ぎには注意してください。
硫化アリルについて別でまとめてありますのでご参照ください。
参考ページ:玉ねぎの硫化アリル(イソアリイン)について
ニンニクの栄養・効能を活かす効果的な料理法

ニンニクの栄養・効能を活かすため、以下の効果的な料理方法をおすすめします。
あくまでも、栄養を活かすためであって、美味しさを追求する場合の料理方法とは異なることをご承知ください。
【ニンニクの栄養・効能を活かす効果的な料理法】
- 細かく刻み、10分放置する
- 加熱する
- ビタミンB1が豊富な食材と合わせる
- 新鮮なものを選ぶ
①細かく刻み、最低10分放置する

ニンニクの効果を最大限に発揮するには、酵素アリイナーゼが活性化させ、アリインを生成しなくてはいけません。
細胞を破壊すればするほど酵素が反応するため、「おろす>みじん切り>繊維に垂直に切る>繊維に沿って切る」となって、調理に合わせてできる限り細胞を壊すように切ります。
また、アリイナーゼの酵素反応は緩やかに反応しますので、切ってから調理または生で食べる前に、最低10分おくと良いことが推奨されています(Song K, Milner JA. The influence of heating on the anticancer properties of garlic. J Nutr. 2001;131(3s):1054S-1057S.)。
②加熱する

アリシンを加熱することでスコルヂニンが発生します。
スコルヂニンは、新陳代謝を促し、疲労回復効果があります。
また、末梢血管拡張作用により血のめぐりをよくする働きがあり、高血圧や動脈硬化、心筋梗塞や脳梗塞などの予防にも効果が期待できます。
ニンニクを生で大量に食べると殺菌作用で腸内環境に悪影響がありますが、加熱をするとその影響を和らげられます。
③ビタミンB1が豊富な食材と合わせる

アリシンはビタミンB1の吸収を助けるため、ビタミンB1を豊富に含む食材と相性が良いです。
ビタミンB1が豊富な食材として、豚肉・大豆・鰹節などが挙げられます。
トンテキが良い組み合わせとして紹介できます。
④新鮮なものを選ぶ

アリインなどの硫化アリルは揮発性物質なので、新鮮なものを選ぶと効能を充分に発揮できます。
水分を多く含んでいるものがより新鮮なので、ふっくらと丸くずっしりとしたものを選びましょう。
外国産のものが安くてお求めやすいですが、国産の方がより新鮮で栄養としても優れています。
特に、「青森県の福地ホワイト六片種」は非常に甘みがあって、外国産のものと比較して別格なのでおすすめです。
まとめ

ニンニクの栄養・効能を活かす効果的な料理法についてまとめました。
栄養を生かす調理の方法に併せて、品質の良い食材を手に入れることも重要です。
残念なことに品質の良い食材を買ってみようと思っても、近所のスーパーの品揃えがない・価格高いなどの問題にあたってしまいます。
そこで旬で良質な野菜を手軽に安く手に入れる方法として、『野菜の宅配定期便』を紹介させて頂いておりますので、ぜひご覧ください。
農家による経験・知恵によるところもありますが、栄養をしっかり摂るためには正しい情報・データも必要なため、書籍・論文などの文献で勉強しました。
栄養について勉強をした際に使用した書籍をまとめましたので、興味がありましたらご参照ください。