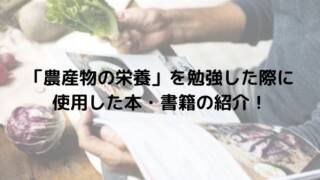食材の栄養素は料理の仕方次第で大きく変化します。
栄養を大きく損なう調理をしてしまうと、食材の栄養素を活かすことができません。
逆にちょっとした工夫・要点を知るだけで、効率的に栄養を活かすことができます。
今回は「ニラ」の栄養・効能を活かす効果的な料理方法をまとめます。
目次
ニラの主な栄養・効能

【ニラの注目成分】
- βカロテン:3500μg
- ビタミンC:19mg
- ビタミンK:180μg
- カリウム:510mg
- 葉酸:100ug
- 食物繊維:2.7g
【ニラ 可食部100gあたり成分 七訂日本食品標準成分表より】
ニラは、ビタミンがバランスよく含有されているマルチビタミン野菜であり、特に抗酸化作用があるβ-カロテンが豊富です。
よく使用されるニラは「葉ニラ」に分類され、それ以外にも日光を当てずに栽培したニラもやしとも言われる「黄ニラ」、つぼみと花茎を食べる「花ニラ」があります。
ニラの英名は「Chinese chive」と表記するように、原産地の中国では葉は韮白という生薬です。
カリウムも豊富で塩分の取り過ぎによるむくみ対策に役立ち、食物繊維は腸内環境を整えるのに役立ちます。
これらの栄養素以外にも注目すべき成分として、硫化アリルが挙げられます。
硫化アリル(メチイン)
ニラに含まれる硫化アリル(メチイン)は、硫黄化合物でシステインスルフォキシド類に分類されるファイトケミカルです。
メチインは、アリイナーゼという酵素が反応して、香り成分の「S-メチルメタンチオスルフィネート」になり、がん細胞抑制効果・殺菌効果などが期待できます。
高知大学の島村先生の研究では、ピロリ菌抑制効果も認められています。
タマネギを例にあげていますが、硫化アリルについては別でまとめます。
参考ページ:玉ねぎの硫化アリル(イソアリイン)について
ニラの栄養・効能を活かす効果的な料理方法

ニラの栄養・効能を活かすため、以下の効果的な料理方法をおすすめします。
ニラに含まれる栄養素で特に変化しやすいのは「硫化アリル」ですので、これに主眼を置いています。
あくまでも、栄養を活かすためであって、美味しさを追求する場合の料理方法とは異なることをご承知ください。
【ニラの栄養・効能を効果的に活かす料理方法】
- 細かく刻み、10分放置する
- 葉先・根本もしっかり使う
- 水につけない
- 油と一緒に食べる
- ビタミンB1を含む食材と一緒に食べる
①細かく刻み、最低10分放置する

ニラの効果を最大限に発揮するには、酵素アリイナーゼが活性化させなければなりません。
細胞を破壊すればするほど酵素が反応するため、細かく刻んでできる限り細胞を壊すように切ります。
また、アリイナーゼの酵素反応は緩やかに反応しますので、切ってから調理または生で食べる前に、最低10分おくと良いことが推奨されている。(Song K, Milner JA. The influence of heating on the anticancer properties of garlic. J Nutr. 2001;131(3s):1054S-1057S.)
②葉先・根本もしっかり使う

ニラの葉先にはβカロテン・ビタミンC・ビタミンEが豊富で、根本には硫化アリルが葉先の4倍ほど含まれています。
匂いが強い部分でもあるので、捨てている方もいるかもしれません。
ニラの葉先・根本は栄養が豊富なので、ぜひこの部分を食べてください。
③水につけない

水につけることで、辛味を抜くことでき、食べやすくなります。
しかし硫化アリルは水溶性なため、水溶性ビタミンと共に流れ出てしまいます。
そのため、水につけて放置することは推奨していません。
④油と一緒に食べる

βカロテンは脂溶性で、油に溶ける性質を持っているので、油と一緒に摂取することで効率よく吸収できます。
ドレッシングをかけて食べるときは、ノンオイルよりも油分が多いドレッシングが好ましいです。
豚ニラ・ニラ玉が相性良く、油と一緒にニラを食べて栄養の吸収率をあげましょう。
⑤ビタミンB1を含む食材と一緒に食べる

硫化アリルはビタミンB1の吸収を高めてくれるので、疲労回復に効果的です。
硫化アリルはビタミンB1の吸収を助けるため、ビタミンB1を豊富に含む食材と相性が良いです。
ビタミンB1が豊富な食材として、豚肉・大豆・鰹節などが挙げられます。
レバニラ炒め・豚ニラ・ニラ玉が非常におすすめなレシピです。
まとめ

ニラの栄養・効能を活かす効果的な料理方法についてまとめました。
栄養を生かす調理の方法に併せて、品質の良い食材を手に入れることも重要です。
残念なことに品質の良い食材を買ってみようと思っても、近所のスーパーの品揃えがない・価格高いなどの問題にあたってしまいます。
そこで旬で良質な野菜を手軽に安く手に入れる方法として、『野菜の宅配定期便』を紹介させて頂いておりますので、ぜひご覧ください。
農家による経験・知恵によるところもありますが、栄養をしっかり摂るためには正しい情報・データも必要なため、書籍・論文などの文献で勉強しました。
栄養について勉強をした際に使用した書籍をまとめましたので、興味がありましたらご参照ください。