ベルクマンの法則とアレンの法則は、19世紀に提唱されて以来、恒温動物の形態的適応を理解する基盤を形成しています。
生物の環境適応戦略を熱力学的視点から解明する重要な理論です。
ベルクマンの法則とアレンの法則が適応できる実例や適応できていない例などを通して、その違いについて知って頂ければと思います。
ベルクマンの法則

ベルクマンの法則(Bergmann’s rule)は、「同種または近縁種の恒温動物において、寒冷地域の個体群が温暖地域の個体群よりも体サイズが大きくなる傾向にある」という法則です。
放熱量は体表面積(体長の2乗)に比例し、熱生産量は体積(体長の3乗)に比例するため、体長が大きくなるほど体温が上がりやすくなります(2乗3乗の法則)。
温暖な気候では体温維持に放熱促進する必要があるため小型になり、寒冷な気候では放熱抑制する必要があるため大型なる方が、熱効率の観点から有利です。
1847年にドイツの生物学者クリスティアン・ベルクマン(Carl Georg Lucas Christian Bergmann)が提唱しました( Christian Bergmann, 1847. “Über die Verhältnisse der wärmeökonomie der Thiere zu ihrer Grösse.” Göttinger Studien, Göttingen, 3(1): 595-708.)。
ヘビ・カエル・コオロギなどの変温動物においては、寒冷地に行くほど小型のものが生息する傾向が見られるため、「逆ベルクマンの法則」と呼ばれることもあります。
ベルクマンの法則の実例
ベルクマンの法則で取り上げられる典型的な事例として、以下のものが挙げられます。
- クマ属の比較:ホッキョクグマ(体長2.5~3m)>ヒグマ(1.5~2.8m)>マレーグマ(1.2~1.5m)
- 日本におけるシカの比較:エゾシカ(体重120~200kg)>ニホンジカ(40~70kg)>ケラマジカ(25~40kg)
また、人間でもベルクマンの法則に従うように、イヌイットなどの極地の人々の体重は中緯度の人々の体重より大きいという報告もあります( Holliday, T. W., & Hilton, C. E. (2010). Body proportions of circumpolar peoples as evidenced from skeletal data: Ipiutak and Tigara (Point Hope) versus Kodiak Island Inuit. American Journal of Physical Anthropology: The Official Publication of the American Association of Physical Anthropologists, 142(2), 287-302. )。
ベルクマンの法則への批判
ベルクマンの法則には例外で当てはまらないことが多いため、法則の一般性への疑義は提示されています。
例えば、北米に生息する20種のコウモリの体の大きさの時空間的変動について、体温の保持が容易さ(熱保存仮説)よりも資源利用可能性・気候変動が体サイズに強く相関することが示されました(Alston, J. M., Keinath, D. A., Willis, C. K. R., et al. (2023). Environmental drivers of body size in North American bats. Functional Ecology, 37(4), 1020-1032.)。
熱適応だけでなく、捕食回避・採餌効率・移動能力・繁殖能力など多面的選択圧が体サイズの変化に寄与します。
また、羽毛や脂肪組織の断熱効果、行動的適応(巣作りや群集形成)、血管構造の変化など、表面積以外の熱調節機構が無視されている点にも注意が必要です。
アレンの法則

アレンの法則(Allen’s rule)とは、「同種または近縁種の恒温動物において、温暖地域の個体群が寒冷地域の個体群よりも突出部(耳、吻、首、足、尾など)が大きくなる傾向にある」という法則です。
温暖な気候では体温維持に放熱促進する必要があるため体表面積を増やし、寒冷な気候では放熱抑制する必要があるため体表面積を減らす方が、熱効率の観点から有利になります。
1877年にアメリカの動物学者ジョエル・アサフ・アレン(Joel Asaph Allen)が提唱しました(Allen, J. A. (1877). The influence of physical conditions in the genesis of species. Radical review, 1, 108-140.)。
アレンの法則の実例
ベルクマンの法則で取り上げられる典型的な事例として、以下のものが挙げられます。
- 耳の大きさ:北極圏に生息する「ホッキョクギツネ」<サハラ砂漠に生息する「フェネック」
- 尾の長さ:スリランカに生息する「トクモンキー(Macaca sinica)」標高が上がるにつれて相対的な尾の長さが短くなる(Huffman, M. A., Kumara, R., Kawamoto, Y., Jayaweera, P. M., Bardi, M., & Nahallage, C. A. D. (2020). What makes a long tail short? Testing Allen’s rule in the toque macaques of Sri Lanka. American Journal of Primatology, 82(4), e23113)
人間でも、北極圏のモンゴロイド(特にエスキモーやアレウト族)において、「鼻腔が狭い」「頭が比較的大きい」「頭が長く丸い」「あごが大きい」「体が比較的大きい」「手足が短い」という形態的特徴があることが示されました( Steegmann Jr, A. T., & Platner, W. S. (1968). Experimental cold modification of cranio‐facial morphology. American journal of physical anthropology, 28(1), 17-30.)。
アレンの法則への批判
ベルクマンの法則と同様に当てはまらない例外が多く、アレンの法則の一般性への疑義は提示されています。
ノウサギ属Lepusを対象とした調査では、体長あたりの耳長と緯度に負の相関はありませんでした(岸茂樹. (2015). 北アメリカのノウサギはアレンの法則に従わない (< 特集> クライン研究を成功させるために). 日本生態学会誌, 65(1), 61-64.)。
また、陸生鳥類107科6974種において、アレンの法則に顕著に従う科は少数であり(107科中89科:81%)、適用範囲や限界を再評価しベルクマンの法則と補完的に使うべきであることが示されています(Baldwin, J. W., Garcia-Porta, J., & Botero, C. A. (2023). Complementarity in Allen’s and Bergmann’s rules among birds. Nature Communications, 14(1), 4240.)。
まとめ

「ベルクマンの法則」と「アレンの法則」についてまとめました。
ベルクマンの法則とアレンの法則は、動物の形態と気候条件の関係を考える上で大事な原理です。
2つの法則が同時に適応できることがあり、ホッキョクグマ(Ursus maritimus)ではヒグマより体が大きく耳は小さいという特徴が現れます。
ただ、これらの特性差の主要因が温度・緯度に関係あると安易に決定付けることはできず、適応範囲について精査する必要はあるようです。
生態学についてより深く勉強するのに、おすすめの書籍をまとめていますのでご参照ください。


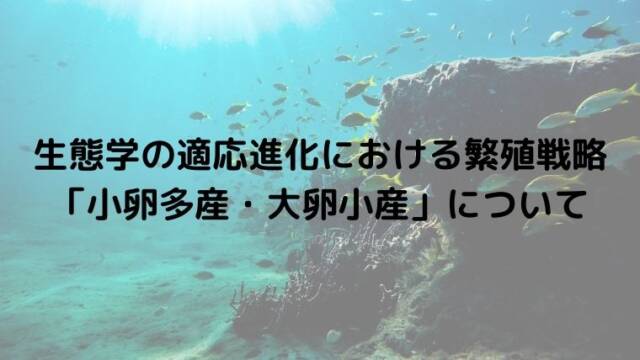

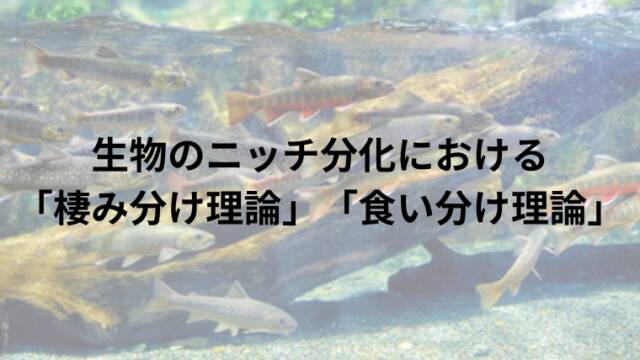

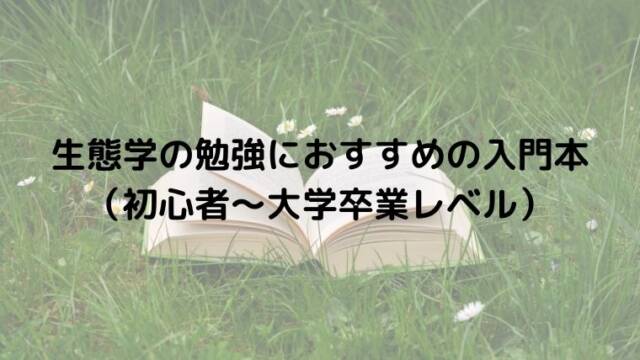
」について-640x360.jpg)

