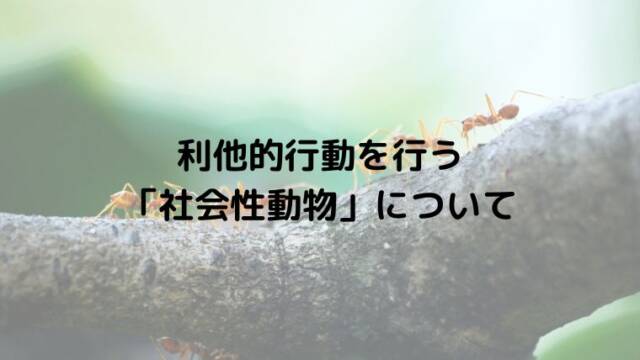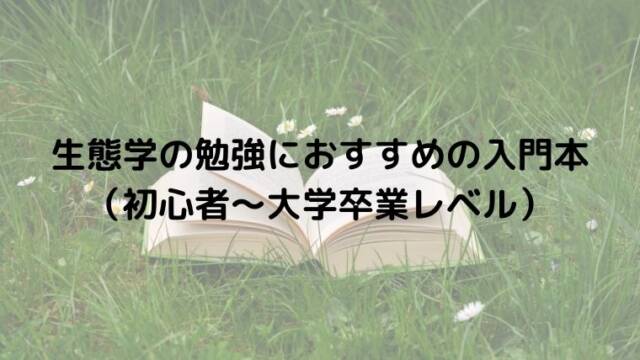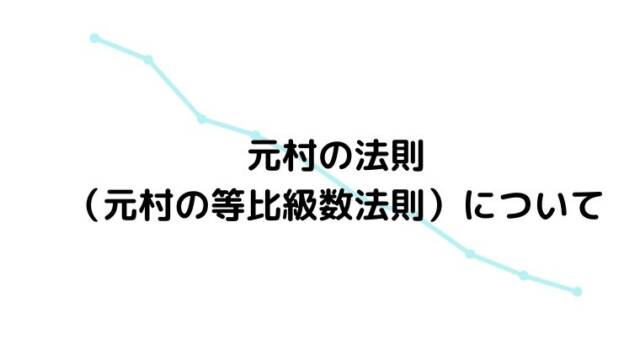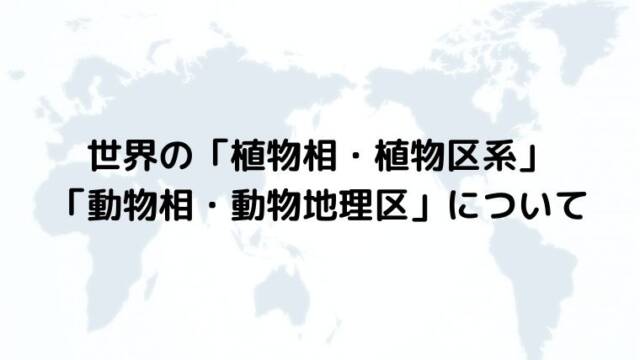進化論・自然選択の理解を深めるため、産業革命以後の急速な自然環境の変化は重要な研究対象となりました。
保護色による擬態がによる進化である例として、「工業暗化(industrial melanism)」が特に有名です。
工業暗化の歴史・科学的な調査、そしてそれに対する批判や反論に焦点を当て、産業革命が生物多様性に与えた深い影響を探ります。
工業暗化(industrial melanism)

工業暗化(industrial melanism)は、工場からの排出される煤煙によって周辺の森林樹皮が黒ずみ地衣類が死滅したため、その地域に生息する蛾の体色が明色から暗色に変化したことです。
19世紀の産業革命時イギリスのマンチェスターで、オオシモフリエダシャク(Biston betularia)に起き、淡色型から暗化型へ表現型が変化しました。
蛾の隠蔽色化と鳥の選別的捕食が自然選択による進化である代表例になります。
工業暗化を示した「ケトルウェル」「マイケル・マジェラス」の実験

産業革命以前のオオシモフリエダシャクのほとんどは淡色型であったことは、標本個体から調べることができます。
暗化型最初の個体は、1848年にマンチェスターで捕獲され、1895年までにマンチェスターにおける暗化個体の頻度は98%にまで達しました(Steward, R.C. (1977). “Industrial and non-industrial melanism in the peppered moth Biston betularia (L.)”. Ecological Entomology 2: 231–243.)。
暗化型個体の割合の増加に関する情報は乏しいため、大気汚染が減少すると暗化型の頻度が減少するのか検証されています。
Henry Bernard Davis Kettlewelが1953年にバーミンガムのCadbury Nature Reserveで行われた実験では、マーキングしたオオシモフリエダシャクを汚染された林野の木の幹へと放って再捕獲する実験を行いました。
再捕獲で生き残った割合は暗化型27.5%・標準型13.0%になり、工業暗化を裏付ける結果です。
後述するが、ケトルウェルの実験手法には科学的な正当な批判が多く指摘されている。
そのためMichael Eugene Nicolas Majerus(マイケル・マジェラス)は、以下の項目を調整したより精巧な実験を2000~2007年に実施されました。
- 蛾の密度
- 放蝶タイミング(昼間・夜間)
- 飼育個体と他地域の野生個体と自生個体
そこで、ケトルウェルの実験の批判への反証ができ、工業汚染による環境の影響が引き起こす差別的捕食の影響の違いは「オオシモフリエダシャクの工業暗化の主要な要素である」と示されました。
工業暗化への批判

「鳥の捕食以外にも自然選択の構成要素があるのでは?」という議論の余地はあるものの、工業暗化は科学的なプロセスで認められています。
ただ、実験の手法に不備があったことから、進化論に懐疑的な派閥から多くの批判が出ている。
- John William Heslop-Harrison:汚染物質が生物の体細胞と生殖細胞の変化の原因となり得るという「化学的誘発仮説」
- Harrison&Garrett:大気中の汚染粒子に含まれていた鉛やマンガンの塩がメラニン生成の遺伝子に変異を引き起こす「突然変異圧仮説」
工業暗化の否定に火をつけた最大の原因は、生物学者ジェリー・コインの「40年以上の観察で木の幹の上にはオオシモフリエダシャクが二個体しか見つからなかった」などの発言です。
マイケル・マジェラスの実験で反証されたが、工業暗化を認めない動きは未だに散見される。
まとめ

工業暗化についてまとめました。
この工業暗化は、短期間で観察された進化の代表的な例として、自然選択による進化を説明する重要な証拠となっています。
生態学についてより深く勉強するのに、おすすめの書籍をまとめていますのでご参照ください。