農業は1年に1作しかできないものが多く、圧倒的に経験・知識が不足してしまいます。
農業に従事し続けるには、勉強し常に新しい知見を学ばねばなりません。
勉強方法として、業界セミナー・先進地訪問・普及員による指導などありますが、私は本・業界誌・論文などを用いて勉強することが好きです。
その一環として『マッキンゼーが読み解く 食と農の未来』を読みましたので、書評・要約のように綺麗に整理できていませんが、感想・勉強になった内容をまとめてみます。
目次
『マッキンゼーが読み解く 食と農の未来』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:
- 出版社:日本経済新聞出版
- 発売日:2020/8/22
- ページ数:248ページ
【目次】
- 序 章 日本農業を取り巻く環境変化を読み解く
- 第I部 食と農を変える八つのメガトレンド
・第1章 農業を取り巻くマクロエコノミクスの変化
・第2章 農業の未来を変える技術革新
・第3章 政策・規制の変化が農業に及ぼす影響
・第4章 食習慣・食生活の変化
・第5章 農業ビジネスをリードする上流プレイヤー
・第6章 世界に訪れる消費者ニーズの変化
・第7章 代替品・代替手法の登場
・第8章 新規参入プレイヤーの台頭 - 第II部 日本の食と農の未来
・第9章 日本農業に期待される新たな挑戦
・第10章 日本農業のポテンシャルを最大に発揮するために
『マッキンゼーが読み解く 食と農の未来』は、世界的なコンサルティング企業マッキンゼーによる大局観が得られる農業戦略白書です。
マッキンゼーの顧客である世界的な農業関係企業を通して、食糧・農業動向の分析・農業ビジネス改革のレポートなど、蓄積されてきたマッキンゼーの内外の食糧・農業関連の知見を初めて書籍としてまとめた1冊です。
農業ビジネスへの新規参入を考えている・官僚・研究者にとっても有益な情報がえられる内容になっていると紹介されています。
アンドレ・アンドニアンはマッキンゼー日本支社長、川西剛史はマッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイトパートナー農業博士、山田唯人はマッキンゼー・アンド・カンパニー パートナーで世界経済フォーラムに (ダボス会議)に出席するなど、最先端の現場の第一人者です。
『マッキンゼーが読み解く 食と農の未来』を読んで勉強になったこと
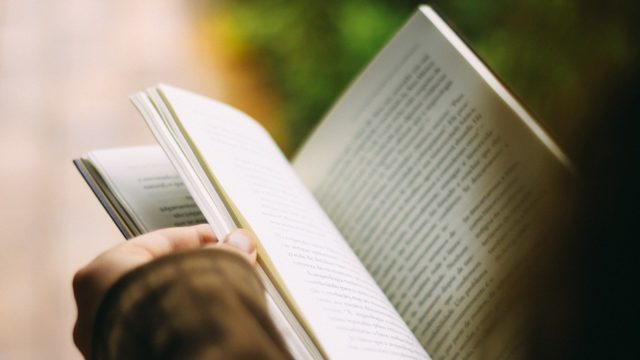
『マッキンゼーが読み解く 食と農の未来』は、食と農のグローバル・メガトレンドを、以下の8つのポイントが整理されています。
- 大状況の変化
- アグリテックなどの抜本的な技術革新
- 政策・規制の変化
- 食習慣・ソーシャルファクターの影響
- 農薬・種子・肥料など上流プレイヤーの変化
- 消費者ニーズの変化
- 代替品・代替手法の進化
- 新規参入プレイヤー
これらが日本農業にどのような影響を及ぼすのかを解説し、日本農業の生産性向上に何が必要か、進むべき方向と解決策は何かを提言しています。
章ごとに重要だと思った箇所をまとめます。
第1章 農業を取り巻くマクロエコノミクスの変化
世界の農業の全体に影響を及ぼす要因として、以下のものが挙げられています。
- 世界的な人口の増加
- 中間所得層の拡大
- 輸出入の構造変化
- 温暖化や水資源の枯渇など栽培環境の変化
2030年には世界の人口は85億人・発展途上国の中間所得層は340万世帯まで拡大します。
そのため、今後の20年で農産物の需要が1.5倍に膨れ上がります。
肉需要は中国で局地的に伸びるなど、品目別・国別での成長市場を見極めて、輸出戦略・農産物生産計画を立てていく必要があります。
世界の貿易取引金額を見ると、小麦が圧倒的に多く、大豆・とうもろこし・砂糖が続きます。
小麦の主要輸出国の推移を見ると、2001年は米国・カナダ・オーストラリアが中心でしたが、2015年にはロシア・ウクライナの輸出量が北米に並ぶほど急進しました。
わずか15年でトレードフローが大きく変化することもがあり、慎重に戦略を立てる必要があります。
農産物のコストは各国に大きな差はなく、補助金・税金などのわずかな変化が国の輸出競争力に大きな影響を与えます。
温暖化も輸出競争力に影響を与える要因になり、南半球では温かくなりすぎて土地生産性が低下し、北半球では氷が溶けて農用地が増えます。
これら温暖化・食糧需給の増加に伴い、水資源・農地が不足することになります。
水資源は2030年には過去20年に比べ3倍弱の水資源開発が必要になり、農地は2030年には4800万ha不足すると予測されています。
第2章 農業の未来を変える技術革新
世界の農業を変える技術革新において、3つのトピックが挙げられています。
- デジタルの活用
- ゲノム編集技術
- バイオ製剤・生物農薬
従来の農業を抜本的に変えるような農業テクノロジー(アグテック)として、
圃場のモニタリングや播種に活かすリモート技術・自動運転やロボティクスといった設備型技術・生産者の判断を助けるAIなどが開発・導入されています。
まだ、日本では狭小な農地に対応するものは少なく、価格の面でも簡単に導入できるものではない点が問題です。
栽培技術だけでなく、育種についてもCRISPR-Cas9によるゲノム編集技術が導入されます。
病原菌への耐性・温度変化への順応性など、様々な性質を持つ作物が作られる可能性があります。
バイオ技術の発達により、生物由来の成分から作られたバイオ製剤の市場規模が2026年に9000億円にまで成長すると言われています。
残留農薬の危険や・環境負荷への懸念などの問題を解決する1つの手段として注目されています。
第3章 政策・規制の変化が農業に及ぼす影響
農産物の平坦なコストカーブの下では、補助金・関税の動きが市場構造を大きく変え、各国のポジションが入れ替わる可能性もあります。
中国では競争力の低い国内農業を保護するコストが高騰してしまい、保護政策を緩和してトウモロコシの輸入を本格化する兆しがあります。
補助金政策の転換が図られると、世界の輸出入のバランスは大きく崩れます。
ゲノム編集技術によっても世界の輸出入のバランスは崩れる可能性もあります。
日本の農業としてどんな形質の作物を作らなければいけないのか考えなければなりません。
日本でも2019年に届出を行えばゲノム編集植物の市場流通が可能になり、食品表示ついうても義務化せず任意の表示になります。
第4章 食習慣・食生活の変化
肉の消費傾向が上がってきており、環境への負荷が懸念されています。
牛肉の生産は、他の家畜と比較して生産に必要な土・水などの資源が多くかかり、温室効果ガスの発生も多いので、環境負荷が特に大きいという事実があります。
そこで、「Meat 2.0」という植物由来のタンパク質を用いることで、持続的な食環境を形成しつつあります。
今後10年以内に食肉市場での代替肉のシェアが10%までに拡大すると、フィナンシャル・タイムズ紙で報じられています。
食肉以外でタンパク質を摂ることができる食材で、人気のあるものに大豆があり、スナック類・パン・菓子・ベビーフード・ミルク・ドリンクなど幅広く取り入れられています。
大豆以外にも、藻類・昆虫食・微生物・培養合成物質などで新たな代替タンパク質源の開発が行われています。
まだこれらの生産コストは高いため、新たなイノベーションを実現するには消費者の知識と理解を深め、規制の枠組みを整備することが必要です。
健康志向の高まりによる食習慣の変化は、砂糖の消費にも表れ、インド・ブラジル・オーストラリアといった国で作っても売れない可能性があります。
第5章 農業ビジネスをリードする上流プレイヤー
肥料・農薬・種子などを提供する化学企業(プレイヤー)の中でも、大手上流プレイヤーが2018年前後に大型M&Aによって統合されて巨大企業になりました。
以下の3つの巨大企業が誕生しており、業界全体の50%のシェアを持っています。
- ダウとデュポン
- バイエルとモンサント
- シンジェンタと中国化工集団
こうしたガリバー企業がいる環境で、シェネリック農薬を主体に高い営業力で競争する企業が現れています。
世界農薬販売量の41%がジェネリック農薬であるが、日本ではわずか5%のシェアしかなく、導入が遅れています。
2017年以降、農薬登録時に有効成分と不純物の組成を定めて管理する仕組みを整えました。
肥料については減量が国内で採掘できないので、海外に頼らざる負えない立場であるので、輸出国と有効な関係を継続して安定的な供給を進めていく必要があります。
第6章 世界に訪れる消費者ニーズの変化
日本国内では米の需要が低下し、約20年間で20%減少しています。
魚については、2016年度の魚介類消費量は2001年度比で60%に留まるなど、多く減少しています。
一方で、日本の農産物は香港・台湾・中国などではニーズがあります。
種類・量ともに豊富な農産物が輸出されており、りんご・なしなどの果物や牛肉が需要が高いです。
また、食事を通した体験に価値を見出されており、チェーンやデパートよりも小さな独立系ショップやこだわりの専門店での買い物が増えています。
もの自体よりも、作られる過程のストーリーを売りにつなげる傾向が広がっています。
第7章 代替品・代替手法の登場
農業には、土地・労働力・農業資材・調達資金など、営むために必要な要素が多くあります。
近年では、これらの一部について、代替・置き換えが進んでいるようです。
フィルムを利用して作物を育てる方法だと、農地が不要になり、どこでも農業ができるようになります。
農地が不要であるため、コンテナ型の植物工場を都市の小規模企画に配置して、立地を生かした鮮度による農産物の付加価値向上・作物の輸送コスト低減を図る試みもされています。
また、資金調達面でも変化があり、クラウドファンディングで資金を集める方法で農業を営む農家も出てきました。
第8章 新規参入プレイヤーの台頭
製造業・農業機械メーカー・ハードウェア企業などが農業に参入してきました。
日本ではトヨタ・イオン・NEC・ソフトバンクなどが、農業の課題解決に向けて農業分野に飛び込んでいます。
世界では、アグリテック企業を支えるため、アクセラレータ・インベスター・アグリインサイトエキスパートの3つのグループがエコシステムを形成しており、日本での整備が求められてます。
- アクセラレータ:資金調達や経営を学ぶプログラムを提供
- インベスター:農業・食品分野に対して投資・資金援助
- アグリインサイトエキスパート:圃場提供・実証試験のアドバイザー
第9章 日本農業に期待される新たな挑戦
農業は、「栽培計画→土地・労働力の確保→資材調達→栽培→物流・販売」というステップを踏んで行われます。
各ステップごとの課題と、改善機会がまとめられています。
- 栽培計画
・課題:生産者の作りたいものを作る「プロダクトアウト」
・改善:実需要から逆算した栽培計画を立てる「マーケットイン」 - 土地・労働力の確保
・課題:農地情報がまとまっておらず、労働力は地域コミュニティに依存
・改善:農地情報の一元化、人材プールとのマッチング - 資材調達
・課題:思い思いの選択
・改善:土壌診断等の検証を重ね、ベストな組み合わせ・プロセスを設計 - 栽培
・課題:指標等の定型化ができておらず、技術継承が困難
・改善:栽培方法をレシピ化、自動化にも横展開 - 物流・販売
・課題:出荷量・需要量が直前で決まるので、物流ルート・市場価格が不安定
・改善:データに基づく予測で、最適化した物流ルート、価格ヘッジ
第10章 日本農業のポテンシャルを最大に発揮するために
消費者の食に対するニーズは多様になり、腹を満たすだけでなく、1つの「体験・目的」を楽しむようになりつつあります。
この価値観は消費者が農業のバリューチェーン全体から提供されることを求められています。
そのため、日本農業のポテンシャルを最大に発揮するためには、全体の流れを統率する「オーケストレーター」によって、バリューチェーンの各プレイヤー間にある壁を取り払い、「コネクト」された食料供給システムを実現する必要があります。
これを実現する方法として、サブスクリプション型の「食体験提供」サービスが挙げられています。
『マッキンゼーが読み解く 食と農の未来』を読んで今後勉強すべきこと

『マッキンゼーが読み解く 食と農の未来』を読んで、今後の農業がどうなっていくのか、もっと知る必要があるように感じました。
こうした最新の知識について、書籍化されるまで待っていると、どうしても後手に回ってしまいます。
そこで、農業雑誌を読むことで、なるべく早く正確な知識を勉強することに努めたいと思います。
おすすめの農業雑誌をまとめてますので、ご参照ください。
まとめ
『マッキンゼーが読み解く 食と農の未来』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介させていただきました。
農業の今後を注視しながら、自分でも実践できるような技術・知識を取り入れていきたいと思います。
サブスクリプション型の農業販売スタイルについて、野菜の定期便などで現在導入が進んでおりますので、ぜひ利用してみてください。

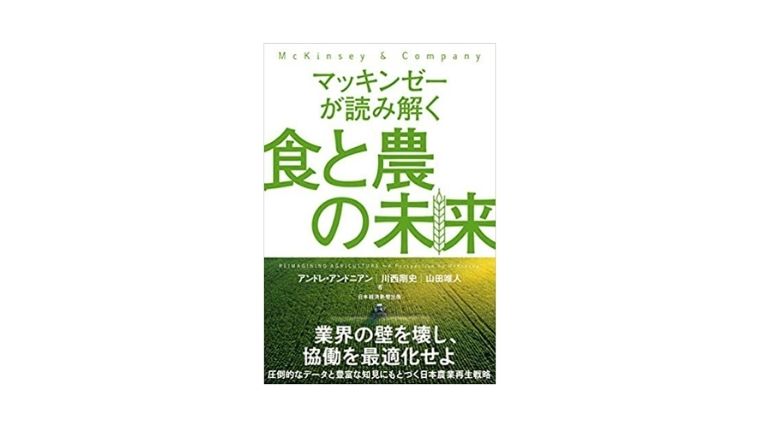

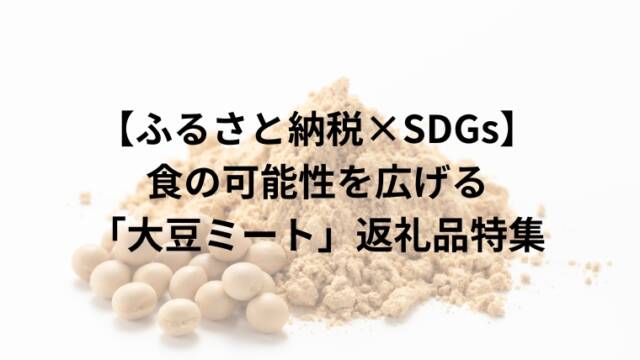

の-メリット・デメリットまとめ-640x360.jpg)
製造メーカーおすすめ5選-640x360.jpg)
で-注視されている添加物まとめ-640x360.jpg)


