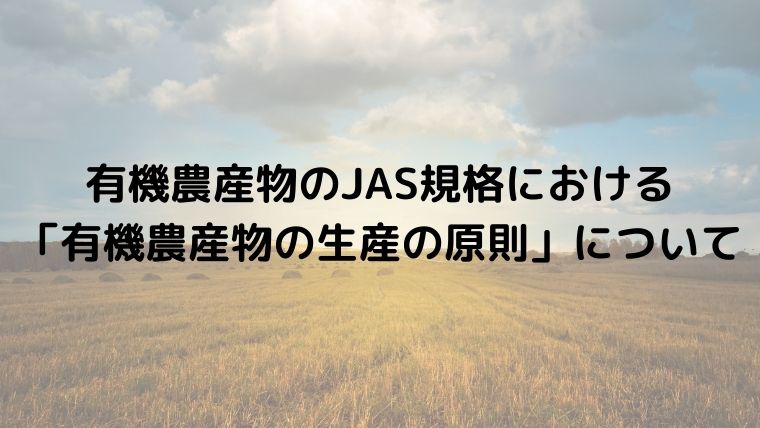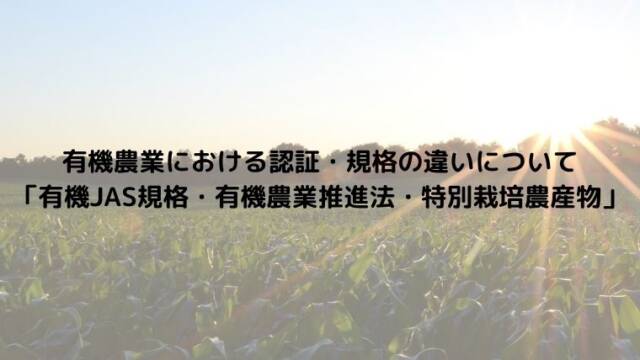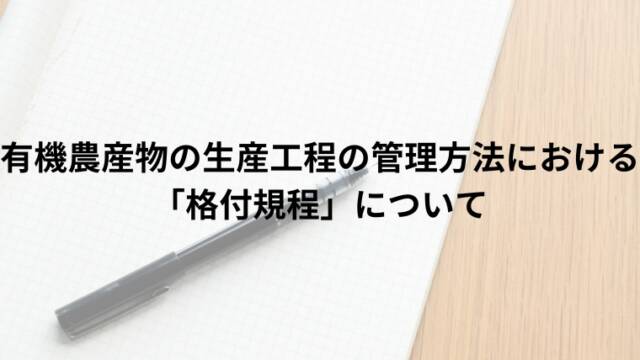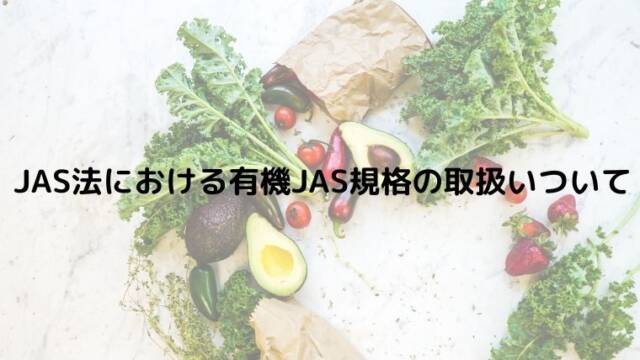有機農産物のJAS規格は、主に次の3つの項目で構成されている。
- 有機農産物の生産の原則
- 生産の方法についての基準
- 有機農産物の名称の表示
生産にあたっては「有機農産物の日本農林規格(JAS 規格)」に定められた栽培方法により農産物を生産し、この規格に準拠したものに格付して出荷しなくていけません。
今回は、3つの項目から、「有機農産物の生産の原則」についてまとめさせていただきます。
目次
有機農産物のJAS規格における「有機農産物の生産の原則」について

有機食品の検査認証制度では、生産組織へ要求する基準として「認定の技術的基準」が定められており、生産方法として「有機農産物の日本農林規格(JAS 規格)」が定められています。
有機農産物のJAS規格第2条には「有機農産物の生産の原則」が定められており、目的と方法が規定されています。
目的:農業の自然循環機能の維持増進を図ること。
- 方法1:化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本とすること。
- 方法2:土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させること。
- 方法3:農業生産に由来する環境への負荷を出来る限り低減した栽培管理方法を採用すること
これはIFOAM(International Federation of Organic Agricultural Movement:国際有機農業運動連盟) が定める「有機生産及び加工の基礎基準」の中にある、有機生産と加工の基本的な活動指針「健康の原理・生態的原理・公正の原理・配慮の原理」の考え方を含んでいます。
方法1:化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本とすること。

肥料及び土壌改良資材(別表1に掲げるものを除く )、農薬(別表2に掲
げるものを除く)並びに土壌、植物又はきのこ類に施されるその他の資材
(天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものを除く。)
をいう。引用:有機農産物の日本農林規格 禁止資材
有機栽培は単に農薬を減らしたり、化学肥料を有機質肥料に置き換えばいいというものではありません。
肥料については、禁止資材として明記されており、この禁止資材に該当しない以下の3つの肥料について施肥が認められています。
- 禁止資材の対象外にしていされた肥料
- 天然物質に由来する肥料
- 化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの
これらについては以下のような肥料が該当しています。
| 肥料及び土壌改良資材 | 基準 |
| 植物及びその残さ由来の資材 | 植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理を行っていないものであること。 |
| 発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材 | 家畜及び家きんの排せつ物に由来するものであること。 |
| 油かす類 | 天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油の抽出を除く)を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
| 食品工場及び繊維工場からの農畜水産産物由来の資材 | |
| と畜場又は水産加工場からの動物性産品由来の資材 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
| バーク堆肥 | |
| 草木灰 | |
| 木炭 | |
| 泥炭 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ |
| 発酵した食品廃棄物由来の資材 | 食品廃棄物以外の物質が混入していないものであること。ただし、土壌改良資材としての使用は、野菜(きのこ類及び山菜類を 除く。)及び果樹への使用並びに育苗用土としての使用に限ること。 |
| メタン発酵消化液(汚泥肥料を除く。) | 家畜ふん尿等の有機物を、嫌気条件下でメタン発酵させた際に生じるものであること。ただし、し尿を原料としたものにあっては、食用作物の可食部分に使用しないこと。 |
| グアノ | – |
| 乾燥藻及びその粉 | |
| 食酢 | |
| 製糖産業の副産物 | |
| 軽焼マグネシア | |
| 硫黄 | |
| 塩化カルシウム | |
| 炭酸カルシウム | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(苦土炭酸カルシウムを含む。)であること。 |
| 天然りん鉱石 | カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであること |
| 塩化加里 (塩化カリウム) | 天然鉱石を粉砕又は水洗精製したもの及び海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたものであること。 |
| 硫酸加里苦土(硫酸加里と硫酸マグネシウムの複塩) | 天然鉱石を水洗精製したものであること。 |
| 水酸化苦土 | 天然鉱石を粉砕したものであること。 |
| 硫酸加里 (硫酸カリウム) | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
| 硫酸苦土(硫酸マグネシウム) | |
| 石こう(硫酸カル シウム) | |
| 生石灰(苦土生石灰を含む。) | |
| 生石灰 | 上記生石灰由来するものであること。 |
| 微量要素(マンガン、ほう素、鉄、 銅、亜鉛、モリブデン及び塩素 | 微量要素の不足により、作物の正常な生育が確保されない場合に使用するものであること。 |
| 岩石を粉砕したもの | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、含有する有害重金属その他の有害物質により土壌等を汚染するものでないこと。 |
| ベントナイト・パーライト・ゼオライト・バーミキュライト・けいそう土焼成粒・鉱さいけい酸質肥料 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
| 塩性スラグ | トーマス製鋼法により副生するものであること。 |
| よう成りん肥 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであること。 |
| 塩化ナトリウム | 海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたもの又は採掘されたものであること |
| リン酸アンモニウム | カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであること。 |
| 乳酸 | 植物を原料として発酵させたものであって、育苗用土等のpH調整に使用する場合に限ること。 |
| 肥料の造粒材及び固結防止材 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。ただし、当該資材によっては肥料の造粒材及び固結防止材を製造することができない場合には、リグニンスルホン酸塩に限り、使用することができる。 |
| その他の肥料及び土壌改良資材 | 植物の栄養に供すること又は土壌を改良することを目的として土地に施される物(生物を含む 及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物(生物を含む であって、天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(組換えDNA技術を用いて製造されていないものに限る であり、かつ、病害虫の防除効果を有することが明らかなものでないこと。ただし、この資材は、この表に掲げる他の資材によっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ることができない場合に限り、使用することができる。 |
また、具体的に使用が認められている農薬は以下のものが該当しています。
| 農 薬 | 基 準 |
|---|---|
| 除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤 | 除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。 |
| なたね油乳剤 | |
| マシン油エアゾル | |
| マシン油乳剤 | |
| デンプン水和剤 | |
| 脂肪酸グリセリド乳剤 | |
| メタアルデヒド粒剤 | 捕虫器に使用する場合に限ること。 |
| 硫黄くん煙剤 | |
| 硫黄粉剤 | |
| 硫黄・銅水和剤 | |
| 水和硫黄剤 | |
| 石灰硫黄合剤 | |
| シイタケ菌糸体抽出物液剤 | |
| 炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹 | |
| 炭酸水素ナトリウム・銅水和剤 | |
| 銅水和剤 | |
| 銅粉剤 | |
| 硫酸銅 | ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。 |
| 生石灰 | ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。 |
| 天敵等生物農薬 | |
| 天敵等生物農薬・銅水和剤 | |
| 性フェロモン剤 | 農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とするものに限ること。 |
| クロレラ抽出物液剤 | |
| 混合生薬抽出物液剤 | |
| ワックス水和剤 | |
| 展着剤 | カゼイン又はパラフィンを有効成分とするものに限ること。 |
| 二酸化炭素くん蒸剤 | 保管施設で使用する場合に限ること。 |
| ケイソウ土粉剤 | 保管施設で使用する場合に限ること。 |
| 食酢 | |
| 燐酸第二鉄粒剤 | |
| 炭酸水素カリウム水溶剤 | |
| 炭酸カルシウム水和剤 | 銅水和剤の薬害防止に使用する場合に限ること。 |
| ミルベメクチン乳剤 | |
| ミルベメクチン水和剤 | |
| スピノサド水和剤 | |
| スピノサド粒剤 | |
| 還元澱粉糖化物液剤 |
天敵等生物農薬は平成24年時点において、以下のものが記載されています。
- BT水和剤、BT粒剤(生菌、死菌を問わない)
- ボーベリア ブロンニアティ剤
- バーティシリウム レカニ水和剤
- ペキロマイセス フモソロセウス水和剤
- ボーベリア バシアーナ乳剤
- スタイナーネマ カーポカプサエ剤
- スタイナーネマ グラセライ剤
- モナクロスポリウム フィマトパガム剤
- パスツーリア ペネトランス水和剤
- チリカブリダニ剤
- ククメリスカブリダニ剤
- ミヤコカブリダニ剤
- コレマンアブラバチ剤
- サバクツヤコバチ剤
- オンシツツヤコバチ剤
- イサエアヒメコバチ剤
- ハモグリコマユバチ剤
- イサエアヒメコバチ・ハモグリコマユバチ剤
- ハモグリミドリヒメコバチ剤
- アリガタシマアザミウマ剤
- ショクガタマバエ剤
- タイリクヒメハナカメムシ剤
- ナミテントウ剤
- ナミヒメハナカメムシ剤
- ヤマトクサカゲロウ剤
- チャハマキ顆粒病ウイルス・リンゴコカクモンハマキ顆粒病ウイルス水和剤
- ズッキーニ黄斑モザイクウイルス弱毒株水溶剤
- タラロマイセス フラバス水和剤
- トリコデルマ アトロビリデ水和剤
- アグロバクテリウム ラジオバクター剤
- 非病原性エルビニア カロトボーラ水和剤
- シュードモナスフルオレッセンス水和剤
- バチルス ズブチリス水和剤
- ドレクスレラ モノセラス剤
- ハスモンヨトウ核多角体病ウイルス水和剤
- コニオチリウム ミニタンス水和剤
- チチュウカイツヤコバチ剤
- バリオボラックス パラドクス水和剤
- ペキロマイセス テヌイペス乳剤
- スワルスキーカブリダニ剤
- バチルス シンプレクス水和剤
- チャバラアブラコバチ剤
方法2:土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させること。
 有機農産物の生産では、健康な土づくりを目指して土壌改良を行い、地力を高め、肥沃な土壌にする必要があります。
有機農産物の生産では、健康な土づくりを目指して土壌改良を行い、地力を高め、肥沃な土壌にする必要があります。
そのためには、土壌の物理性・化学性・生物性を指標とする肥沃度を考えなければいけません。
- 土壌の物理性:土壌の硬さ・作土の厚さ・緻密度・保水性・透水性・通気性
- 土壌の化学性:陽イオン交換容量・養分の保持力・pH・酸化還元
- 土壌の生物性:土壌生物の豊かさや有機物分解性
これらは相互的な関係にあるため、総合的に土づくりを実施する必要があります。
3つの特性に有効な土づくりには、有機物の施用が必須です。
物理性においては土壌の団粒構造の促進、化学性においては地力の指標の改善、生物性においては土壌生物の多様化が図られます。
物理性
団粒構造とは、粘土鉱物が微量要素などと共に有機物の微生物分解によって生成された腐植・土壌動物の糞などにより互いにくっつきあって出来た隙間だらけのかたまりです。
団粒構造が発達した土壌の物理性は以下のような特徴があります。
- 土が柔らかい
- 作土層が厚い
- 不透水層がない
- 保水性が良く排水性が良い
- 通気性が良い
- 三相分布(固相、気相、液相)が適切である
物理性改善の為の具体的管理方法として、次のような方法が考えられます。
- 客土・深耕・天地返し・心土破砕による作土層の改善
- 明渠・暗渠による排水・透水性の改善
- イネ科などの深根性で根張りの良い緑肥作物を栽培し鋤き込む方法
- マメ科植物を植え、根粒菌を集め地力窒素を高める
化学性
地力が高いとは、以下の化学性が高いことです。
- 地力窒素
- 陽イオン交換容量の保持力
- pH緩衝能
地力窒素とは、有機態窒素の中で微生物によって徐々に分解され無機態になりうる有機態窒素のことで、アンモニア態・硝酸態の無機態窒素です。
窒素分を有機物施用で補い、微生物分解により微生物にとって余分な無機態窒素を土壌に補い蓄えます。
陽イオン交換容量(CEC)が高いと言うことは、陽イオンであるアンモニウム・カリウム・カルシウム・マグネシウムなどの保持力の高さ、つまり保肥力の高さです。
有機物施用により土壌中に腐植が増えることにより保肥力を高めることができ、バーミキュライト・モンモリロナイト・ゼオライト・腐植酸質資材などの土壌改良資材の施用でも保肥力が高まります。
団粒構造の発達した土壌では、陽イオンや陰イオンを吸着する粘土鉱物や腐植がより多く集積しているので、pHの急激な影響が少なくなるという利点もあります。
生物性
土壌動物として、以下が代表で挙げられます。
- ミミズ
- トビムシ
- ダニ
- センチュウ類
ミミズは、土づくりにおいて最も重要視され、植物残さなどの有機物分解による堆肥化やその排泄物である糞による土壌団粒構造の促進を図ってくれます。
糞には濃縮された土壌養分や植物 成長促進物質やカルシウムが含まれ、ミミズが掘った穴は通気性や通水性を高める。
トビムシやダニ類は土壌表面の腐植層に生存し、粗大有機物や糸状菌の菌糸を餌に生活しています。
センチュウ類は土壌有機物や微生物を餌にするものや、ネグサレセンチュウのように植物の根に寄生して生育を阻害するものもある。
また、土壌中には多種多様な微生物が生息し、有機物の分解による無機化という役割があります。
土壌の浄化・土壌肥沃度の向上・作物への養分供給など土づくりの面で有益な面と、連作障害などのように土壌微生物バランスの偏りによる土壌病害や作物の生育阻害の原因になるなど有害な面もあります。
種類は、5種類に大別されます
- 細菌
- 放線菌
- 糸状菌
- 藻類
- 原生動物
細菌は一般的にバクテリアと呼ばれ、土壌微生物の中で最も小さく多く見られる微生物で、乳酸菌・酢酸菌・納豆菌・枯草菌・亜硝酸菌・硝酸菌・硫黄細菌・鉄酸化菌など、多種多様です。
糸状菌は一般にカビと呼ばれ、粗大有機物の骨格となるセルロースやリグニンなどを効率的に分解し、他の微生物が分解し易いようにします。
放線菌は抗生物質を生産する菌群で、特有の臭いも出し土特有の臭いは放線菌によるところが多く、セルロースやリグニンの分解に関与し、生産する抗生物質によって糸状菌や細菌を抑制する働きもあり、この働きを利用した各種微生物資材が存在します。
藻類とは「ラン藻類」のことで、このラン藻と共生するアカウキクサを水田に増やし、それによりの土壌に窒素を補給する水稲栽培を実施しているところもあります。
原生動物は、ミドリムシ・アメーバ・ゾウリムシなどが菌類が分解したものを食べるデリネーターとして必須です。
また、大気中の窒素ガスを体内に取り込むことが出来る微生物を窒素固定菌と呼んでおり、とっても重要な役割を果たします。
方法3:農業生産に由来する環境への負荷を出来る限り低減した栽培管理方法を採用すること

農業が直接的・間接的に環境問題と密接に関わっており、以下の問題の一端であることを強く意識する必要があります。
- 地球温暖化
- オゾン層の破壊
- 重金属による土壌汚染
- 塩類濃度障害
- 土壌浸食
- 砂漠化
- 地下水の枯渇や汚染
- 河川・湖沼の富栄養化
- 水源涵養機能の低下
そのため、有機農業では、これらに配慮した栽培手法を取り入れなければなりません。
まとめ

有機農産物の生産の原則についてまとめました。
有機農業について書籍で勉強をすることができますので、おすすめの本を下記記事にてまとめていますのでご参照ください。