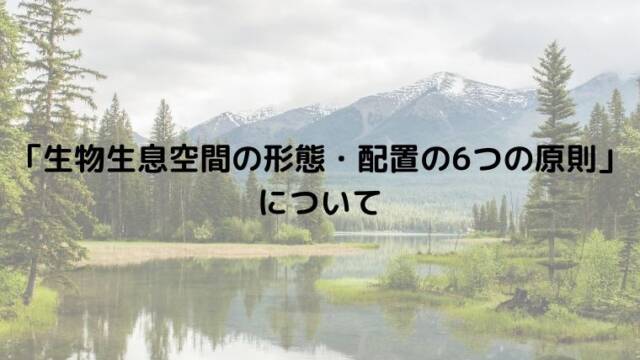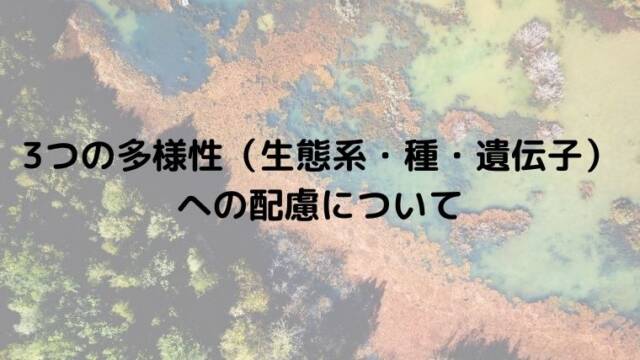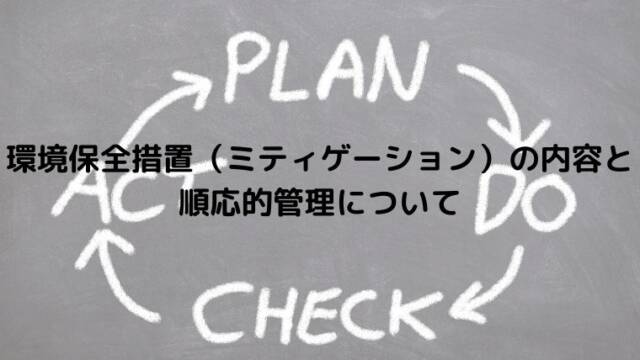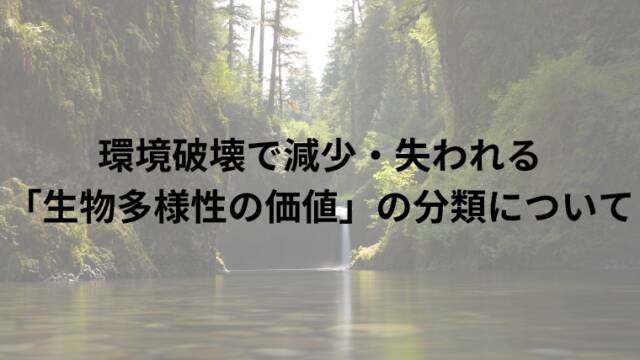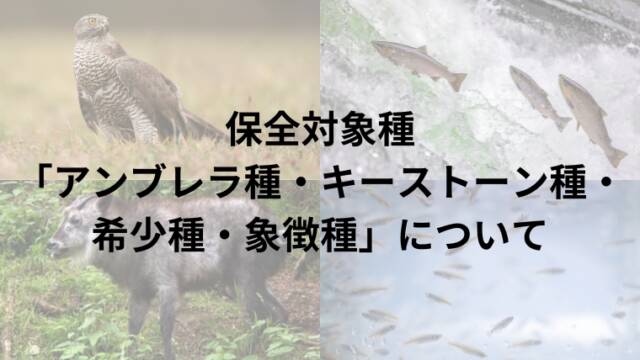保全対象種を選定し、対象となる地域において保全・再生・創出する生態系を決めます。
この方法は、複雑な生態系を簡略化して解釈し、保全・再生・創出がしやすくなる点においてとても秀でています。
保全活動において、科学的・数学的な根拠に基づいて、客観的に必要な対策が実施されることもあります。
しかし、人間の恣意性によって大きな問題が生じてしまうのです。
以下の点について注意が必要になりますので、保全対象種選定の注意点について解説します。
【保全対象種選定の注意点】
- 希少種偏重
- 愛玩偏重
- 循環偏重
希少種偏重

保全対象種には希少種が選ばれ、普通種が蔑ろにされがちです。
希少種を早期に保全しないと絶滅してしまう恐れがあり、早急に対策しなければなりません。
希少種を守ることで、希少種に関連すると思われる動植物の環境は整います。
しかし、生態系はとても複雑で、保全対象に引っかからない普通種が生態系の鍵を握っている可能性があります。
希少種だけを守れば良いと偏重しすぎると、普通種が希少種になるほどの崩壊が起きてしまいます。
希少種保全を中核に起きながらも、その地域の生態系に含まれるすべての種に恩恵のある対策が必須です。
愛玩偏重

どの生物を「可愛い・美しい」と人間が捉えるかという恣意性に注意が必要になります。
保全対象種に、多くの人が好感を抱き、マスコット的な存在であるシンボル種が選ばれやすいです。
地域の生態系にどれだけ必要なのかという学術的視点を完全に無視する形で、好ましいという理由だけでより貴重な種を蔑ろにする保全方法も行われています。
しかし、忌み嫌われやすい生物(特に腐食性の生物)も生態系の一員であり、非常に重要な役割があります。
シンボル種から嫌悪感を与える生物の重要性をしっかり説明・対策が必要です。
循環偏重
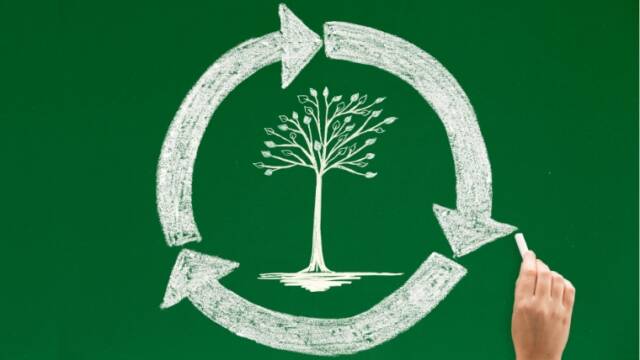
優遇された特定の種に現存量(バイオマス)が偏在し、他の生物への移動を阻害することがあります。
特に環境収容力が増えていないのに優遇種の生息環境だけ整えると、物質循環の停滞を起こし、最悪環境収容力の現象まで引き起こします。
生態系全体が痩せ細り、餌が減ってしまい、優遇種の生息数までも減少します。
また、固定された生態系を望むあまり、自然遷移・自然撹乱の阻害を行い、健全な生態系育成を阻害させます。
これの行き着く先は、定着しないのに生物を毎年放流している愚かな保全活動になります。
種にばかり着目するのではなく、環境収容力が増える対策をしましょう。
まとめ

保全対象種選定の注意点について解説しました。
保全対象種選定される「アンブレラ種・キーストーン種・希少種・象徴種」と呼ばれるカテゴリーがあります。
そちらについては、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。
また、生態学についてより深く勉強するのに、おすすめの書籍をまとめていますのでご参照ください。