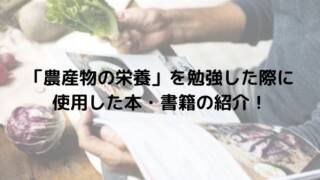食材の栄養素は料理の仕方次第で大きく変化します。
栄養を大きく損なう調理をしてしまうと、食材の栄養素を活かすことができません。
逆にちょっとした工夫・要点を知るだけで、効率的に栄養を活かすことができます。
今回は、「鶏胸肉」の栄養・効能を活かす効果的な料理法をまとめます。
鶏胸肉の主な栄養・効能

【鶏胸肉の注目成分】
- エネルギー:145kcal
- たんぱく質:21.3g
- 脂質:5.9g
- カリウム:340mg
- ビタミンB1:0.09mg
- ビタミンB2:0.10mg
- ナイアシン当量:15.4㎎mg
- ビタミンB6:0.57mg
【鶏胸肉 皮付き 可食部100gあたり成分 七訂日本食品標準成分表より】
鶏胸肉は、もも肉と比べると脂肪が少なくたんぱく質が豊富です。
皮付きは脂質が5.9gですが皮なしなら1.9gになり、脂質を抑えながら良質なたんぱく質を摂取することができます。
主要な栄養以外で、注目するべき成分として「イミダペプチド(イミダゾールジペプチド)」があります。
イミダペプチド(イミダゾールジペプチド)
イミダペプチド(イミダゾールジペプチド)は、アミノ酸の「カルノシン」や「アンセリン」が結合してできた成分で、活性酸素を除去するなどの抗酸化作用・疲労回復に効果的です。
最近では、身体の疲労だけでなく、精神的な疲労回復や認知症の予防にも効果があると言われています。
むね肉にはイミダペプチドが100gあたり1223mgと豊富です。
鶏胸肉の栄養・効能を活かす効果的な料理法

鶏胸肉の栄養・効能を活かすため、以下の効果的な料理方法をおすすめします。
あくまでも、栄養を活かすためであって、美味しさを追求する場合の料理方法とは異なることをご承知ください。
【鶏胸肉の栄養・効能を活かす効果的な料理法】
- 低温調理
- 炭水化物・ビタミンDと合わせて食べる
- ブライン液に浸ける
- 良い肉を選ぶ
①低温調理

たんぱく質は高温で長時間加熱すると変質してしまいます。
また、むね肉はもも肉に比べて脂質が少なく水分が多い部位なので、加熱すると火が通りやすいですが、どうしても水分がぬけてパサつきがちです。
そのため鶏胸肉は低温調理をおすすめします。
低温調理器は最近安価に手に入るようになり、低温調理での調理がしやすくなりました。
サルモネラ菌・カンピロバクターに注意しなければならないので、厚生労働省の特定加熱食肉製品で決められている加熱時間と温度から55℃で55分程度なのですが、安全確保のため「60℃で60分」で調理すると良いです。
家庭で難しい場合は、コンビニやスーパーでサラダチキンそのものが売っていますので、そちらを活用してみると良いでしょう。
②炭水化物・ビタミンDと合わせて食べる

たんぱく質は、炭水化物・ビタミンDと合わせて摂取することで、吸収・筋肉合成が促進されます。
炭水化物は、血糖値の上昇によってインスリンが分泌されることで、アミノ酸が細胞へ取り込まれやすくなります。
ビタミンDは、干ししいたけ・卵に多く、筋肉合成を促します。
鶏胸肉は、チキンライスなど炭水化物と合わせたり、チキンピカタなどのビタミンDが豊富な卵と合わせて食べることがおすすめです。
※ビタミンB群もたんぱく質代謝をサポートしますが、むね肉に含まれているのでここでは省きます。
③ブライン液に浸ける

鶏肉は、パサパサとした食感になりがちです。
そこで、水に対し5%砂糖5%塩を溶かした「ブライン液」に漬け込んでから調理しましょう。
肉の保水性がアップして、ジューシーな食感になりやすいです。
④良い肉を選ぶ

どんな種類のお肉にも共通して良いお肉を選ぶポイントがあります。
- パックの中に肉汁(ドリップ)が出ていない
- 肉の色が黒ずんでいない
- 赤みと脂肪の境目がはっきりしている
できるだけ良い肉を選べるかで、肉の味・栄養が大きく変わってきます。
まとめ

鶏胸肉の栄養・効能を活かす効果的な料理法についてまとめました。
農家による経験・知恵によるところもありますが、栄養をしっかり摂るためには正しい情報・データも必要なため、書籍・論文などの文献で勉強しました。
栄養について勉強をした際に使用した書籍をまとめましたので、興味がありましたらご参照ください。