屋外にビオトープを作ると、冬場の越冬対策が必要になります。
寒さによって、「ビオトープ内の水が全て凍った」「水草がすべて枯死した」など問題が発生し、越冬に失敗した話は枚挙にいとまがないです。
容量の小さなビオトープでは、特に越冬に失敗しないための「冬越しの対策」が必要になります。
実際にビオトープを楽しんでいる筆者が、屋外ビオトープで可能なメダカ・水草の冬越し対策を紹介します。
目次
メダカ・水草に関する「冬越しの基礎情報」

メダカは、水温が10℃を下回ると活性・消化機能も低下して5℃以下で冬眠状態となり、飼育水がすべて凍結しなければ屋外で生存できます。
水温低下で溶存酸素量も増加し、水面だけ凍ったくらいでは酸素不足になることはありません。
ただ、冬眠状態になったら消化不良を起こしやすいので、餌を与えないようにしましょう。
水草は、種ごとに耐寒性が異なり、どんなに頑張っても屋外で越冬不可能な種があります。
熱帯性の水草は室内で管理するか、来年新しく購入することを検討しなければなりません。
飼育する際は越冬可能な在来種がおすすめで、別記事でまとめていますのでご参照ください。
我が家の状況

私のビオトープは、テトラの『じょうろでキレイメダカ鉢』を階段状に設置しています。
ビオトープ・メダカなどの愛好家が一般的に用いる容器よりは少し小さいかもしれません。

我が家はそこまで雪深くない地域ですが、冬季中に積雪深50cmの大雪が降ることがあります。
上記の写真の通り、飼育容器どころかシュロガヤツリ (Cyperus alternifolius L.)が埋まってしまいました。

かまくら効果でビオトープは完全に凍ることはなく、ビオトープ水面上部は雪が溶けて穴が空いています。
肝は冷えますが、メダカや水草など中の生体は皆無事で、しっかり越冬してくれました。
ビオトープの冬越し対策5選

人工的な環境であるビオトープでは、ビオトープ内の生物を無事に冬越しさせ春を迎えさせるために、冬越しの対策が必要です。
ビオトープの越冬対策について、5つのおすすめ対策を紹介します。
【ビオトープの冬越し対策5選】
- 室内越冬・半室内越冬
- 水管理 ~水量多く水深深めに~
- そっとしておく ~餌やりや水換えの禁止~
- すだれや波板で上部を覆う
- 冬までに生体を大きくしておく
冬越し対策①室内越冬・半室内越冬

冬越し対策で1番単純かつ効果的なのが、外より温かい「家の中・サンルーム」などに移動させて室内越冬させることです。
小さい容器であればビオトープごと移動してしまうのも1つの手段で、玄関・軒下・ガレージなど半室内に入れるだけでも、冷気に晒さず雪も入らないので生体への負担が軽減されます。
スペースに限りがある場合は、全ての生体を移動させるのではなく、屋外ビオトープに入っている耐寒性が弱い水草・生体だけでも室内・半室内に移動させましょう。
寒いと引きこもって室内水槽を見がち🥶 pic.twitter.com/FnWzcBGncn
— おいも屋 (@nougyou_doboku) December 6, 2024
私は、メダカを品種ごとに2ペアほど、耐寒性の低いヒメガガブタなどを11月くらいから室内に入れています。
熱帯性の植物だけを集めて、日光の良く当たる場所に移動させ、組み立て式のビニールハウスに入れる方もいます。
20年に1度の大寒波で死滅してしまうリスクはどうしてもあるので、耐寒性があっても「2株だけ」「2ペアだけ」など一部だけついでに室内越冬させれば、全滅の心配はありません。
水流が弱めに設計してある「メダカ専用の水槽」なども売っていますので、そうしたものを容器に活用すれば少し過密でも気になりません。
水草だけなら、「ボトルに入れて越冬させる」「種(殖芽)の状態で保存する」などの方法もあります。
冬越し対策②水管理 ~水量多く水深深めに~

メダカ・耐寒性水草でも、飼育水が凍結すると物理的に生き残ることができません。
しかしビオトープの一部は凍ってしまっても、凍っていないところにメダカは移動できますし、植物体も全部凍らなければ大丈夫です。
表面は凍りやすいですが、水深が深ければ水底まで凍ることはあまりありません。

我が家のビオトープは概ね15cmほどの水深ですが、表面だけの凍るだけでしっかり越冬に成功してくれました。
凍結を予防するために、水量多く水深深めに水管理するのが一般的です。
冬の間でも差水をしっかり行い、水深を深めに維持しましょう。
冬越し対策③そっとしておく ~餌やりや水換えの禁止~

メダカ・水草は、水温低下によって活性・消化機能が低下し、冬眠状態に入ります。
メダカはエサを食べないので、餌やりをしても消化不良・水質悪化を招くだけで良いことはありません。
病原菌・プランクトンも不活性化されているので、水換え・掃除をしてしまうと生体の体力を消耗させてダメージを与えるだけです。
冬越し中は餌は与えず、水換えも行ってはいけません。
そっとしておくため、ビオトープ内に水草がなくなって鳥や猫など狙われやすい場合は、メダカが安心して隠れることができるスペースを作る必要があります。
エアレーションや発泡スチロールを浮かべるなど、水面を動かし凍結防止をする方法が紹介されることがありますが、無駄な負担を掛けるリスクの方が高いのでおすすめしません。
できる限り、冬越し中はそっとしておきましょう。
冬越し対策④すだれや波板で上部を覆う

すだれや波板で上部を覆うのは、夏場の強烈な日差しを遮る暑さ対策の定番です。
これらのグッズは、冬越し時も活用することができます。
すだれや波板で上部を覆うと、外気温・水の蒸発を防いでくれるだけでなく、積雪の圧力分散に非常に効果的です。
水面が凍ると積雪が積み重なり、重みで氷が割れると圧死してしまいます。
豪雪時は、必ずビオトープ上部を覆う対策を実施しましょう。
冬越し対策⑤冬までに生体を大きくしておく

成体でも冬の寒さは厳しいので、稚魚・若株の生存率は高くありません。
そのため、9月には水草の株分け・メダカの採卵は終わらせ、それ以降はやめることをおすすめします。
成長しきれなった小さい個体は、室内に避難させるなどの対策が必要です。
冬越しに入る前に、冬の寒さに耐えられるように生体を大きく成長させておきましょう。
まとめ
【ビオトープの冬越し対策5選】
- 室内越冬・半室内越冬
- 水管理 ~水量多く水深深めに~
- そっとしておく ~餌やりや水換えの禁止~
- すだれや波板で上部を覆う
- 冬までに生体を大きくしておく
メダカ・水草の越冬失敗しないための「ビオトープの冬越し対策5選」をまとめました。
これらの対策を実践すれば、ビオトープは厳しい冬を乗り越え、春には元気な姿を見せてくれるでしょう。
冬の準備は11月くらいから少しずつ始め、なるべく早く実施してください。

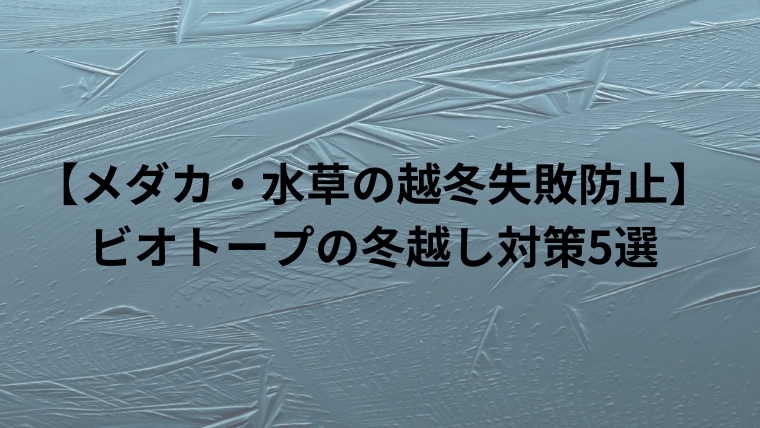


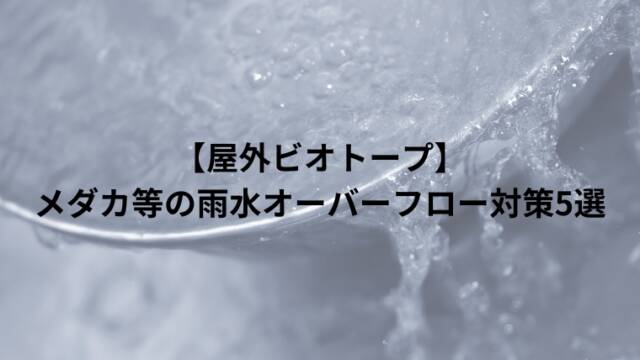



」-640x360.jpg)


