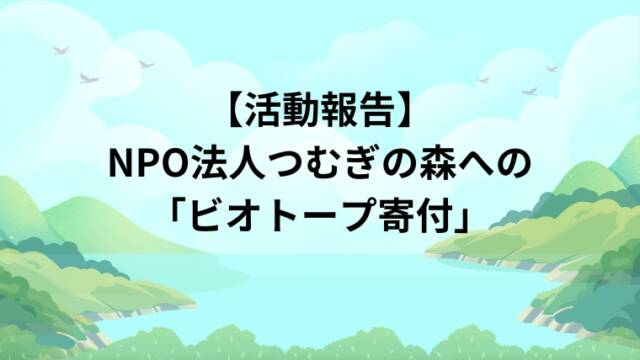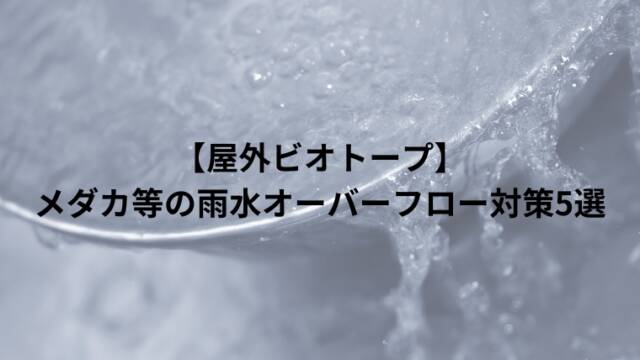駐車場の勾配を利用して「棚田式ビオトープ」を作ってみたところ、『自宅で湿地帯ビオトープ!生物多様性を守る水辺づくり』の企画である自宅で湿地帯ビオトープ大賞にて、DIY賞を頂くことができました。
駐車場で棚田を作ってみました。
テトラの既製品コンテナを活用して、極小スペースの傾斜地でもビオトープを楽しんでいます。#自宅で湿地帯ビオトープ大賞 pic.twitter.com/oWM7ThNkKJ
— おいも屋 (@nougyou_doboku) January 30, 2024
ありがたいことに、DM等で「やってみたい!」「これなんか意味あるの?」など反響がありましたので、自分の考えを記事にまとめさせていただきます。
大したものではありませんが、DMを送ってくれた人に熱意を込めて作成しましたので、他の人にとってはアイデアの種になれば幸いです。
目次
棚田式ビオトープの特徴

棚田式ビオトープ作成のきっかけは、大学で学んだ農業排水を農業用水として循環・再利用する「循環灌漑」を思い出したことです。
反復利用によって排水量減少・汚濁物質の流出減少に効果があり、それをビオトープに導入してみました。
もちろん、上から下に水がチョロチョロ流れるビジュアルが大好きで、なんかロマンを感じたことも重要です。
そんな棚田式ビオトープは、以下の3つの特徴を推しています。
【棚田式ビオトープの特徴】
- 水質を安定させることができる
- 分割管理ができる
- 足し水管理が簡単
- カエルが好む環境が多い
特徴①水質を安定させることができる

コンテナを土中に埋めることができない場合、雨水が流入した時に天端から生体が溢れ出てしまう恐れがあります。
そのため、コンテナを直置きする際は、オーバーフロー対策を施すのが一般的です。
少量の雨ならオーバーフローが上手く機能するだけで済むのですが、大雨の際は雨水でほとんど入れ替わってしまうこともあるでしょう。
アクアリストなら一度は体験する、バクテリアが死滅による「白濁り」が発生することもあります。
棚田式ビオトープなら上流からの古水を下の容器に入れることができるので、大雨の際に起こりやすい雨水による水質・水温の急変を防ぐ効果が期待できます。
有機物・栄養塩とかは植物の成長に欠かせないので、排水を循環させて良いバランスでコンテナ内に栄養状態を維持できているでしょう。
2年くらい「水換え・土砂出し・容器のリセット無し」の差し水だけで、中のメダカ・水草が大量死滅しなかったので、N=1ですが良い環境を構築できていると思います。
特徴②分割管理ができる

複数容器を設置するため、容器ごとに異なる飼育環境を管理をすることができます。
複数の品種・血統の水草・メダカが混ざる心配がありません。
1つの容器で水草の生育形を満足できる広さを用意できれば良いのですが、そんな場所は一般庶民の私には用意できません。
競争に強い植物・弱い植物が混在できる環境を用意できないならば、別容器で育てるのが1番だと判断しました。
現在棚田式ビオトープで飼育している植物は「ヒメコウホネ・アサザ・イトタヌキモ・マツモ・インバモ・ヤエオモダカ・ミズギンバイ・ヒツジグサ・ヌマトラノオ・ミツガシワ・イチョウウキゴケ・ミミカキグサ・ヌマハリイ・ミズトクサ・サギソウ・イシモチソウ・ヒメワタスゲ・姫睡蓮・シラサギカヤツリ・シュロガヤツリ・ミニシペラス・ミズサンザシ・ウィローモス・ロタラ・サラセニア・サスマタモウセンゴケ」です
分割管理のおかげかとても多くの種類を育てられています。
特徴③足し水管理が簡単
「棚田式ビオトープ」の足し水の風景
上流に水入れればあとは自動だし、水が落ちる音が好き😍(近場で工事中)#湿地帯ビオトープ pic.twitter.com/U10LmXW5Kn
— おいも屋 (@nougyou_doboku) May 18, 2024
晴天続きになると、容器内の飼育水がどんどん減ってしまうので「足し水」が必要です。
1つ1つの容器に足し水するのは手間がかかり、メダカ飼育のプロたちは配管を敷いて省力化を図っています。
棚田式ビオトープの場合は、最上流部のコンテナに水を足し続けるだけで余剰分は下流にオーバーフローするので、一気に全部に足し水をすることができます。
最上流部の水質悪化には気をつけなきゃいけませんが、水が階段状にチョロチョロ流れる様子は非常に心地が良いものです。
特徴④カエルが好む環境が多い
メダカ鉢のここは、アマガエルのアパートになるんですね! pic.twitter.com/xmwDHOYHN2
— おいも屋 (@nougyou_doboku) July 25, 2023
可愛い😍
棚田式ビオトープの良さに、カエルが好む環境の多さも追記ですね!#湿地帯ビオトープ https://t.co/tJQAGg1uWb pic.twitter.com/xLDmf52qGK
— おいも屋 (@nougyou_doboku) May 23, 2024
棚田式ビオトープには、オーバーフローの隙間・コンテナ段差の隙間など、日差しを遮ることのできるカエルが好む環境が多くあります。
容器を横に並べるだけではうまれないニッチがあるので、カエルが好きであれば非常におすすめです。
そんな人はいないと思いますが、容器内にオタマジャクシを産んでほしくない人には逆に不向きかもしれません。
棚田式ビオトープの材料


棚田式ビオトープでは、容器にオーバーフロー対策を施し、容器を上下に設置することが必要です。
容器をDIYして制作することができますが、既製品なら手間を省くことができ耐久性も安心できます。
特に、底面で集めた汚れを足し水で押し流すことができる、テトラが販売している「じょうろでキレイメダカ鉢」がおすすめです。
「20,40,40×40,丸30,丸45」の5サイズ、「黒・みかげ・ラメ増しホワイト・色光育成グレー」の4色と選択肢が多くあります。
自作する場合
自作する場合は、コンテナに穴を開けてオーバーフロー加工をしましょう。
【DIYの手順】
- NVボックス・ジャンボタライにドライバ等で穿孔
- L字塩ビパイプ・パッキン・魚流出防止カバーを設置
- 止水コーティング
- 漏水試験
棚田式ビオトープの作り方

棚田式ビオトープの作り方は、とてもシンプルで簡単です。
説明不要かもしれませんが、こだわりと工夫が微妙にありますのでまとめてみました。
【棚田式ビオトープの作り方】
- じょうろでキレイメダカ鉢を組み立てる(容器DIYを完了させる)
- 設置場所を均平にする
- じょうろでキレイメダカ鉢を設置する
- 中身を入れる
①じょうろでキレイメダカ鉢を組み立てる(容器DIYを完了させる)


じょうろでキレイメダカ鉢はパーツが大変少ないです。
説明書もしっかり同梱されているので、組み立ては1分で終わります。


底面すのこからエルボーを通して、足し水をすると底面から排水ができます。
若干エルボー側面の隙間はありますが、基本は底面から排水されるので、オーバーフロー時に卵・種子などの生体が流れ出ることが少ない点も非常に良いです。
②設置場所を均平にする


我が家の設置場所は、砂利斜面なので軽く均して設置するだけで高低差が確保できます。
平らな場所ならばレンガ等を積めば高低差が出せるでしょう。
③じょうろでキレイメダカ鉢を設置する


飼育容器を設置する際には、水を一旦張ってみて排水位置や均平具合を確認しましょう。
自分の場合は砂利の上に設置するので、水を張って重さをつけたあとに砂利の締固めで若干均平に変化が出るため、カルキ抜きだと思って1~2日は生体は何も入れずに放置します。


容器に直射日光が当たると夏場の猛暑時に40℃以上のお湯になりやすくなるので、もしコンテナを土中に埋めることが可能なら埋めましょう。
私の場合配管等の関係で埋めることができなかったので、西側をブロック塀・東側をプランターにおいて容器に当たる日光を遮っています。
30℃を超えてくるとすだれを立てるなど、容器を埋めない際は暑さ対策に工夫が必要です。
④中身を入れる


中身を自由に入れればよいのですが、じょうろでキレイメダカ鉢を使う場合は1つ注意が必要です。
底砂を敷く場合、粒目3mm未満の場合は底面が詰まってしまうので、3mm以上のものにしなければなりません。
それでも自分は詰まりを軽減させたいので、100均の茶こしを底面に設置してから赤玉土を敷いています。

容器内は結構深さがあるので、ダイソーに売っている素焼き鉢を使って高さを確保して植物を植えつけて、メダカなど水域を広めにとっています。
まとめ

棚田式ビオトープについてまとめました。
自宅で湿地帯ビオトープ大賞に参加してから、どんどん調子に乗って受賞した写真から半年でコンテナの数は約2倍になっています。
今後もビオトープの発信を続けていきますので、X(旧ツイッター)のアカウント「おいも屋(@nougyou_doboku)」フォローして絡んでもらえれば嬉しいです。
『自宅で湿地帯ビオトープ:中島淳 (著)・大童澄瞳 (イラスト)』を読んで、一緒に湿地帯ビオトープを楽しみましょう!





」-640x360.jpg)