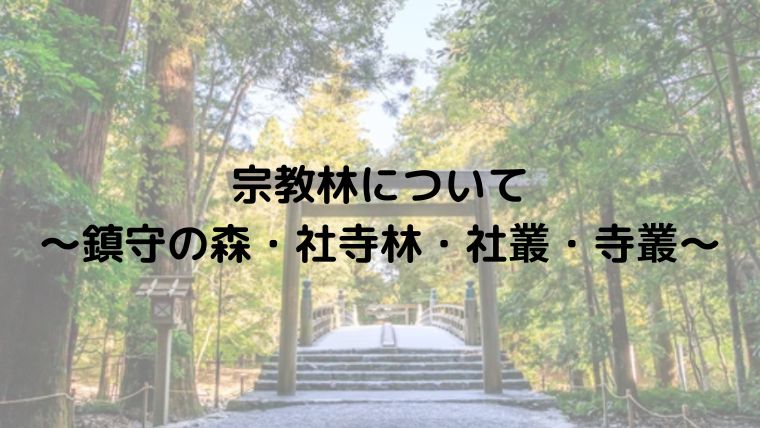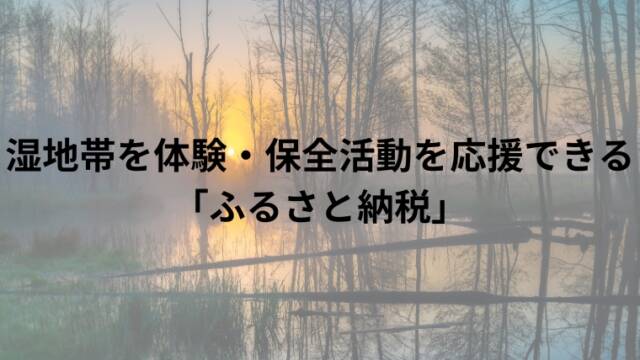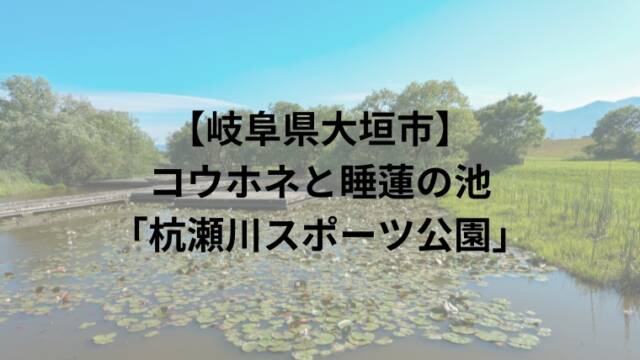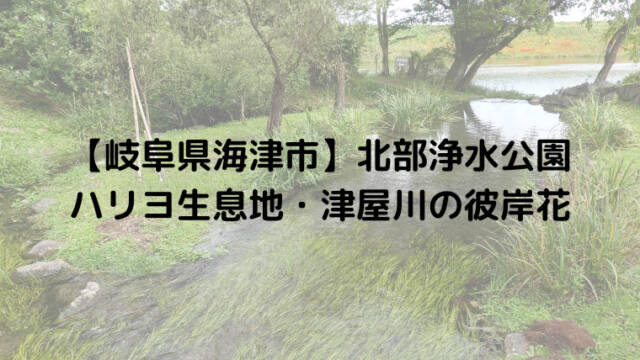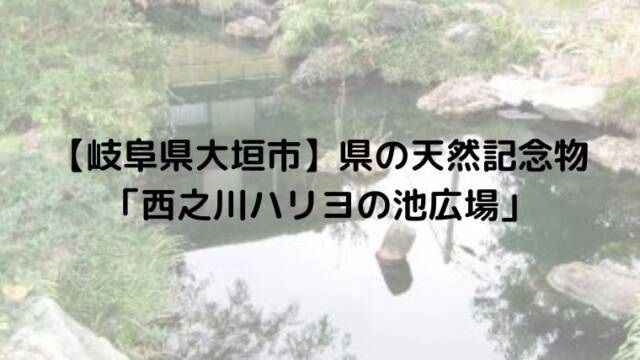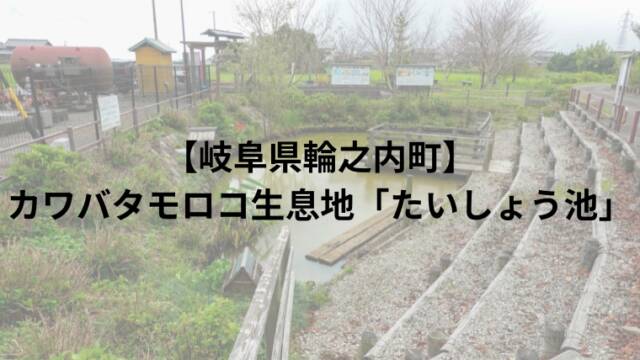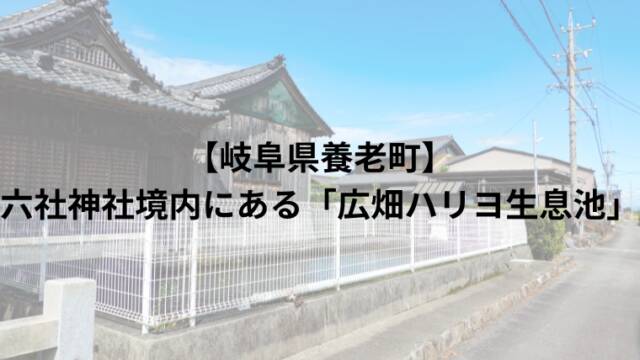神社・寺院の境内には、周囲の景観とは違う規模・樹林密度の森林が形成され、神仏の存在を感じさせる荘厳な空間です。
宗教目的により人為的に造成された森林を「宗教林(religious forest)」と呼び、鎮守の森・社寺林・社叢・寺叢が宗教林に該当します。
人工的な管理が定期的にされるため、「豊かな生態系の場・希少な生物の生息の場」として非常に貴重な場です。
深田 伊佐夫先生の「宗教林に関する研究」を軸に、宗教林についてまとめます。
鎮守の森(sacred forest)について

「鎮守の森(sacred forest)」は、神社と一体になった樹木・森林で、神の依り代として神聖視されるような情緒的景観を伴う複合的な空間のことです。
神道史大辞典では「鎮守は一定の土地や建物を鎮安守護する神」のことを意味し、氏神・産土神と同義で用いられます。
古神道における神奈備(かむなび・かんなび)という神が鎮座する森で、神代・上代(かみしろ)とも呼ばれます。
日本では常緑樹とそれのある空間を神の依り代である常盤木を崇拝する信仰観と、鎮守の社に対する信仰観が結びついて、鎮守の森(鎮守の杜)の概念が形成されました。
明治神宮のような巨大な森林から田園の真ん中にぽつんとある緑の小島まで、社を囲むように鎮守の森は多様な形態を取りますが、社の附属的な意味合いではなく森自身が主役となる場合に鎮守の森と表現されることが多い印象です。
信仰の対象にしてだけでなく、神域・常世と現世を分ける境界のようにも働いています。
また、神社境内で開発が入らなかった「豊かな生態系の場・希少な生物の生息の場」、祭事・行事を行う「地域住民の交流する場」など、多層的な空間としての意味合いも含んでいます。
東日本大震災(2011年)において津波の勢いを減衰させた「防潮林」「防災林」としての役割が注目され、「鎮守の森のプロジェクト」などで災害から命を守る森づくりが促進されています。
「鎮守の森」の例
鎮守の森は各地域にありますが、有名な森として以下を挙げることができます。
- 明治神宮の杜:東京都の明治神宮
- 宮域林:三重県の伊勢神宮
- 春日山原始林:奈良県の春日大社
社寺林(precinct forest)について

社寺林(precinct forest)は、神社や寺院などの宗教施設に付帯する樹林・森林のことで、社寺有林・寺社林とも呼ばれます。
鎮守の森・社叢・寺叢はすべて社寺林に含むことができる包括的な概念です。
社寺林は社寺の森巌(荘厳)さと風致を維持する目的の「境内林」と、林木の販売収益を得るなど所有する教団・宗教法人の財源確保を視野に持つ「境外林」に区分されます。
社寺有林については森林法第2条の民有林に関する定義と規定、境内林・境外林については宗教法人法第3条の境内建物及び境内地の定義と規定がそれぞれ適用され、法的な根拠を伴う物質的側面の概念・定義です。
1970年代には全国の社寺林の総面積は8万haあり、全国森林面積の0.32%にあたります。
この投稿をInstagramで見る
社叢(しゃそう)について

社叢(しゃそう)は、基本的には神社の森のことを指します。
社叢学会の発足により、寺院や宗教的聖地の樹林・森林も含めた概念・定義も有するようになってきました。
社叢とは神社の森、すなわち「神々の森」のことですが、「神々の森」には鎮守の森をはじめとする社寺林、塚の木立、ウタキ(沖縄の聖域)などが含まれます。
引用:社叢学会
文化財保護法・その前身にあたる史跡名勝天然記念物保存法で「社叢」の表記があり、文化財保護法の条文には「名木・巨樹・老木・崎形木・栽培植物の原木・並木・社叢」と表記されています。
現在までに、史跡名勝天然記念物保存法および文化財保護法に指定された社叢は18件あります。
寺叢(じそう)について

寺叢(じそう)は、寺院に付帯する庭園・墓地を含む境内地全体の樹林・森林のことです。
禅林・僧林・叢林などは、寺院自体のことを指すので「樹林・森林」とは異なる概念になります。
仏教の説く浄土世界を庭園造成により表現するなど宗教的な意義を高めるために造設されます。
また、宗教建築物・仏像の建立材確保、寺院運営の財源確保など、寺院の運営のためにも増設されます。
寺叢については、愛知県の蓮華寺寺叢を例に挙げることができますのでご参照ください。
まとめ
| 宗教林の分類 | ||
| 名称 | 対象 | 意味 |
| 鎮守の森 | 神社 | 神社と一体になった樹木・森林で、神の依り代として神聖視されるような情緒的景観を伴う複合的な空間のこと |
| 社寺林 | 神社・寺院 | 神社や寺院などの宗教施設に付帯する樹林・森林のこと。社寺有林・寺社林とも。 |
| 社叢 | 神社が主 | 神社の森を基本として、社寺林・塚の木立・ウタキ(沖縄の聖域)を含む |
| 寺叢 | 寺院 | 寺院に付帯する庭園・墓地を含む境内地全体の樹林・森林 |
宗教目的により人為的に造成された森林「宗教林」についてまとめました。
鎮守の森・社寺林・社叢・寺叢について、概念が重複する点が多く、はっきりとした使い分けがされていないケースがほとんどです。
樹林・森林に対しての実際の名付けの実態を今後確認していきたいと思います。