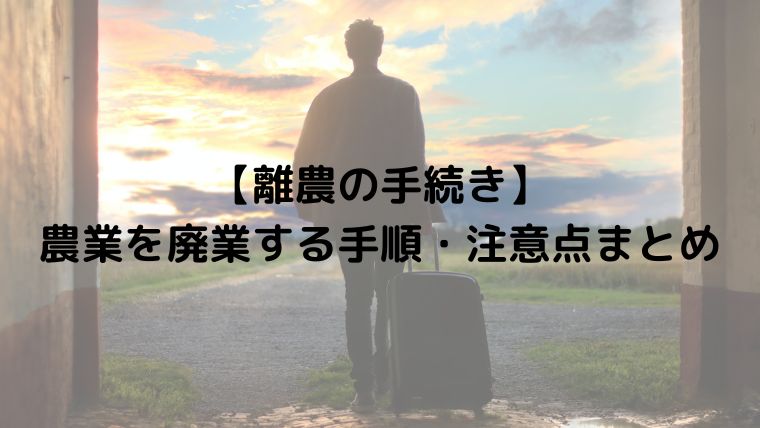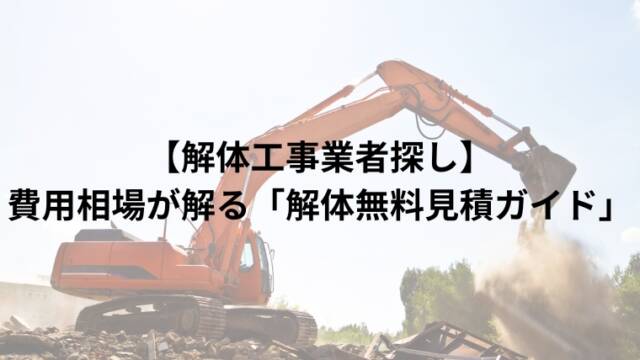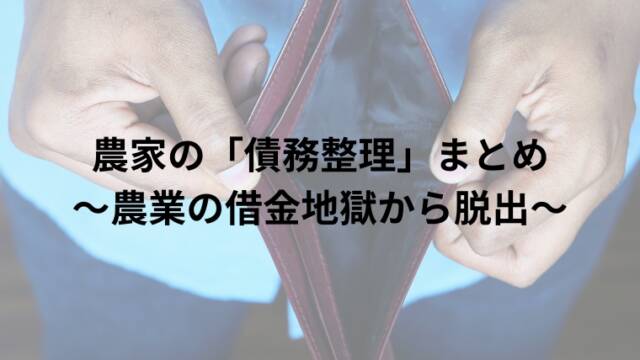離農する農家は増加傾向にあり、基幹的農業従事者は減少傾向が続いており、2015年は175万7千人いたのに対して、2020年は136万3千人と、基幹的農業従事者が5年で22%減少しています。(令和3年度 食料・農業・農村白書 特集)
従事者の約7割が65歳以上であり、高齢化が離農を大きく加速させるでしょう。
高齢化以外にもコスト増で生計が立てられない等、さまざまな理由で離農を選ばざる負えない状態が広がっています。
離農する農家が急増しているため、離農する際に発生する手続きについて簡単にまとめてみることにしました。
目次
離農の流れ

離農の流れは大まかに以下の通りです。
【離農の流れ】
- 「報連相」:農業委員会・土地改良区・農協・銀行等
- 「資産売却」:事業全体・農地・農機具
- 「契約解除」:販売契約・リース・借地等
- 「債務整理」:借金の清算
- 「行政手続き」:廃業届等
この流れに沿って、やらなくてはいけないこと・注意点をまとめてみます。
①「報連相」:農業委員会・土地改良区・農協・銀行等

農業用地は、農業委員会に無断で農業をやめたり、農地を無断売却・転用することはできません。
多くの手続きの窓口は農業委員会になり、農業委員会の意向でスムーズに離農できるかどうかが決まります。
そのため離農する場合は、農業委員会に速やかに報告・相談をしましょう。
また土地改良区・農協の組合員に属している場合は、組合員の資格を損失するため、報告が必要です。
土地改良区に関しては、土地改良区法第42条2項により、負担金に相当分を精算するための決済金を納める必要があるので、早めに連絡しましょう。
②「資産売却」:事業全体・農地・農機具

農業施設・農機具をローンで購入している農家がほとんどで、離農の際に返さないといけないローンがあちこちにある状態でしょう。
資産として活躍していたものも、離農後は固定資産税などの税金がかかり、無駄な出費が増えてしまう負債となってしまいます。
そのため、資産であったものを資産であるうちに早めに処分して「現金化」しましょう。
資産を丸ごと売却するなら、「第三者への事業売却(第三者継承)」がおすすめです。
農地・農機具・農業施設などはもちろん、販売ルート・種子など資産として売りにくいものも評価され、高値で資産を売却できます。
ただ、借金が多い場合は事業売却は厳しいかもしれません。
その場合は、農地・農機具を自身で売却して廃業する道があります。
②-1 第三者への事業売却(第三者継承)

第三者への事業売却は、農地・機械・設備の有形資産だけでなく、技術・ノウハウ・人脈等の無形資産を合わせて売却できます。
事業全体を売却すると、資産を単体で切り売りするよりも割高な価格で売却できるでしょう。
しかし単体で売るよりも売却に時間がかかってしまうので、資産の売却金を借金の返済に充てる予定の場合は適していません。
事業承継・M&Aが普及し始めているため、「成約手数料がゼロ・無料登録できる」事業承継プラットフォームがありますのでぜひご活用ください。
成約までのサポートがある「TownlifeM&A」 がおすすめですので、ぜひお問い合わせください。

②‐2 農地の処分

農地を処分するには、農地法に基づく許可が必要になってきます。
所有権移転を伴う農地法の許可は以下の2種類です。
- 3条許可:農地を農地として売却する場合
- 5条許可:農地を農地以外に転用して売却する場合
3条許可は農業委員会、5条許可は都道府県知事・指定市町村長が行います。
登記地目が農地でなくても、現に耕作されている農地であれば対象です。
これらの許可なく、農地を処分することができませんので、離農の報告を農業委員会にする際に相談しましょう。
許可を取らない場合、農地の原状回復を求められ、従わない場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった罰則が科せられます。
農振地域(青地)の場合、農地転用が認められていないので、農地として譲渡・貸出・売却が必要です。
農地の処分として、主に以下の3パターンになります。
【農地の処分方法】
- 農地を農地以外で使用する
- 農地を貸し出す
- 農地を売却する
【農地を農地以外で使用する】
農地を農地転用できた場合、農地を宅地・雑種地にして活用する方法があります。
農地を宅地にして、アパート・マンションを建てて家賃収入を得る・コンビニ等の商業利用することで、新たな収入源が得られるでしょう。
「太陽光発電施設」「駐車場・コインパーキング」「介護施設・保育施設・医療施設」などの用地として幅広い用途で活用することができます。
【農地を貸し出す】
農地を貸し出す方法として、農地中間管理機構(農地バンク)の利用がおすすめです。
農地中間管理機関を活用することで、大規模農家に貸し出すことができ、賃料が得られます。
また賃料とは別に、「経営転換協力金(旧離農給付金)」が取得できます。
さまざまな条件はありますが、「地域の土地集積に協力し、10年以上貸し付けること」で、10aあたり1万円(1戸25万円が上限)が交付されるので、検討してみましょう。
【農地を売却する】
農地を売却する際には、「農地として売却する」「農地以外として売却する」の2つのパターンが存在します。
農用地以外として売却する方が売却単価が高い傾向です。
一般的な農地売却の流れは、以下の流れです。
- 農地の査定
- 媒介契約
- 売却活動
- 停止条件付き売買契約
- 許可申請
- 引き渡し
という流れになります。
農地を売却すると「譲渡所得税」「登録免許税」「印紙税」「復興特別税」などの税金が発生し、確定申告が必要になるので注意しましょう。
「うまく売却することができない不良物件の場合は、
②‐3 農機具の処分

農機具の多くは固定資産税の課税対象で、トラクターやコンバインは軽自動車税もかかるので、持っているだけ出費が嵩んでしまいます。
時間経過とともに価値も下がってしまうので、早めに処分してしまうことをおすすめします。
農機具の処分として、主に以下の3パターンです。
【農機具の処分方法】
- 農機具を売却する
- 農機具をリースする
- 農機具を譲渡する
【農機具を売却する】
農機具の買取は人気があり、トラクター・コンバイン・田植え機などの大型農業用機械だけでなく、播種機・耕耘機・草刈機などの小型農業用機械も高く売却することができます。
日本国内だけでなく海外でも農機具を売ることができるため、農機具を買取してくれる業者が増えており、売却先に困ることはありません。
しかし適正な価格ではなく安く買い叩く業者・強引に売却を迫る業者が多く、良い印象はありません。
せっかく農機具を手放すなら、高く売却でき、安心できる業者にお願いしたいところです。
一括査定でき、東証上場企業が運営している農機具買取査定君というサービスをおすすめします。
また、大きな農場を経営している場合は、油圧シャベル(ユンボ・バックホー・パワーショベル)・ホイールローダ(タイヤショベル)・ブルドーザーなどの農業用重機・建機もあるでしょう。
これらは農業以外にも土木・建築の業界で活用することができるため、土木・建築の業界に精通している業者に査定を出す方が、高く売却できる可能性が大きいです。
土木・建築の業界に精通し、即現金化できる建機買取.コムをおすすめします。
【農機具をリースする】
コンバイン・トラクターなどの大型農業機械の場合、購入はしたくないけど借りたいという農家が多くいます。
農機具の貸出のプラットフォームがないため、周辺の農家の意向次第ではありますが、農機具をリースすることも可能です。
愛着のある農機具を見知った農家に使ってもらえ、リース料が得られるなら良い選択かもしれません。
リースが切れて誰も使い手が居なくなった場合は売却すれば良いのですが、運転時間が伸びるほど農機具の価値が下がってしまうので注意が必要です。
また、リースのは口約束にするとトラブルが起きやすいので、リース契約締結の内容を書面で必ず残しておきましょう。
【農機具を譲渡する】
耕耘機などの小型農機具や値がつかない農機具は、新しい使い手に譲渡してしまう方法もあります。
農機具はエンジンやバッテリーなどを搭載しているため、「適正処理困難物」に指定されており、粗大ごみとして自治体に処分を依頼することはできません。
不用品買取業者に、出張料・処分料金などを支払って譲渡する方法もあります。
農協によっては、農機具の引取りもしているところがあるので、相談してみましょう。![]()
③「契約解除」:販売契約・リース・借地等

事業売却・継承ができず農産物の生産を中止するならば、販売契約先に速やかに報告にいくべきです。
契約内容によっては、「契約解除は1年前に報告する」など規定があり、調整が必要になります。
個人飲食店など小口に卸している場合は、数量が確保できず相手が困ることもあるので、代替販売先の紹介などケアも忘れずにしましょう。
農機のリースなどしている場合は、契約更新をやめるだけで簡単に済みますが、問題になるのは「借地」です。
「![]() 原状回復で返却すること」が契約に明記されていることがほとんどで、農機具小屋・ビニールハウスの解体・撤去が必要になることがあります。
原状回復で返却すること」が契約に明記されていることがほとんどで、農機具小屋・ビニールハウスの解体・撤去が必要になることがあります。
重機での解体・産業廃棄物の運搬処分はなかなか個人ではできないので、解体業者に依頼しなければなりません。
無料で優良解体業者の見積を比較できる「解体無料見積ガイド」で複数見積りをしてみましょう。
④「債務整理」:借金の清算
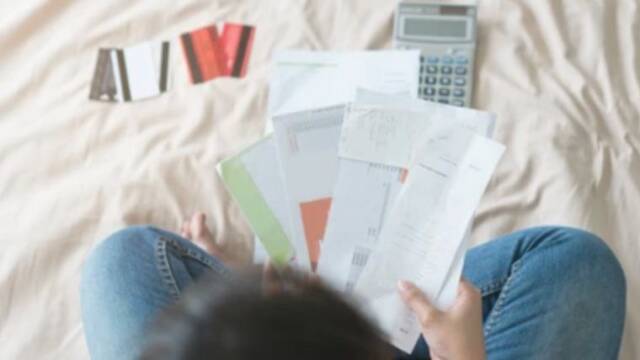
「事業売却ができなかった」「資産売却をしたが借金が残ってしまった」場合は、借金の清算をしなくてはなりません。
借金返済が難しい場合には、債務整理を行う必要があります。
債務整理は、「任意整理・個人再生・破産」の3つに大別され、農業を続ける場合は「任意整理」、農業を続けない・収入が一切ない場合は「自己破産」を選択するのが一般的です。
債務整理は弁護士・司法書士の協力が必要不可欠なので、法律事務所に相談するとスムーズにいきますので、すぐ相談しましょう。
債務整理の詳細については、下記記事をご参照ください。
⑤「行政手続き」:廃業届等

離農をする場合は、農家である資格を損失することに加え、個人事業主としての資格も損失します。
そのため、事業廃止に関する書類の提出が必要です。
税務署には、「廃業届」「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出しましょう。
農業者年金に加入している場合は、解約の申請も必要かもしれません。
法人化している場合は、「清算」「解散登記」が必要になりとても煩雑なので、司法書士等の専門家に依頼することをおすすめします。
まとめ

【離農の流れ】
- 「報連相」:農業委員会・土地改良区・農協・銀行等
- 「資産売却」:事業全体・農地・農機具
- 「契約解除」:販売契約・リース・借地等
- 「債務整理」:借金の清算
- 「行政手続き」:廃業届等
離農の手続きを、大まかではありますがまとめさせていただきました。
離農を検討している方・決断された方の一助になればと思います。