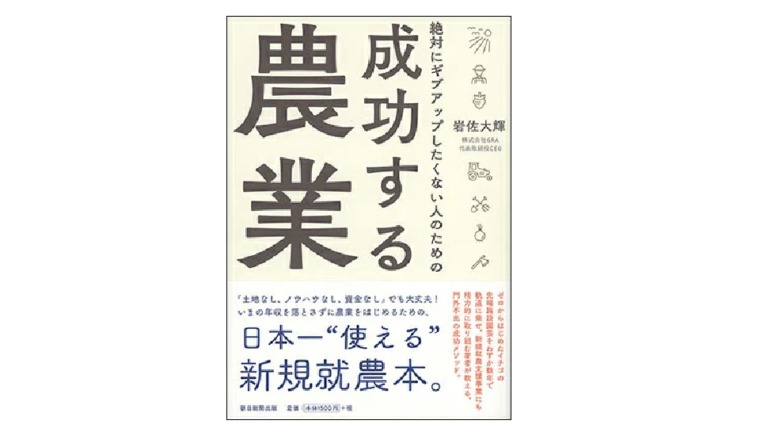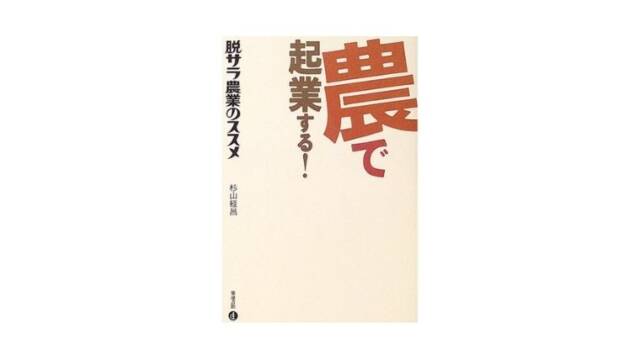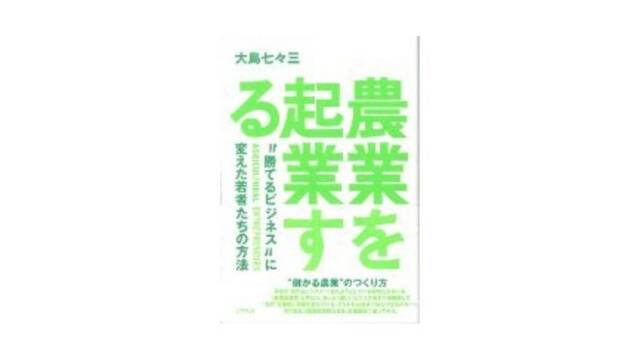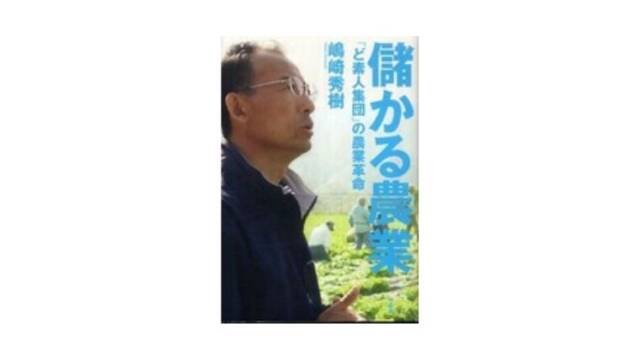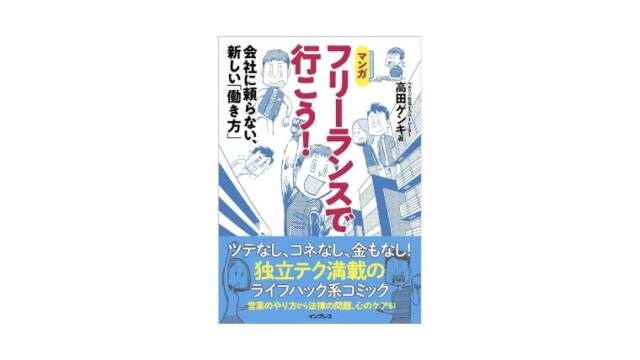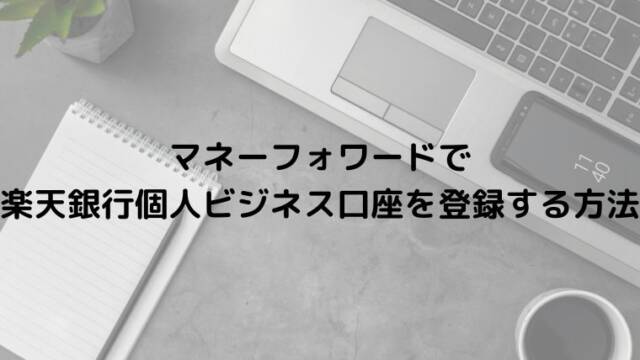新規農業をし、農業従事者の一員になるにはどうしたらいいだろうかと、たくさんの本を読んで勉強しています。
『絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業』を読んでいるだけでは記憶になかなか残りにくいため、インプットした知識を整理して、
- 「読んで勉強になったこと」
- 「理解が及ばず、さらに勉強をしなくてはいけないこと」
を感じたままに書き留めます。
書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介いたします。
目次
- 『絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業』とは?
- 『絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業』を読んで勉強になったこと
- 農業って儲かるの?
- 作物を作ったのに、売れなかったらどうするの?
- 天候が原因で不作になったら、借金まみれになるのでは?
- 農協ってよく批判されているけど、使わないほうがいいの?
- 都会出身の人間が地方に移住してやっていけるもなの?
- 農地を借りる、買うのはやっぱり大変?
- やっぱり修業に何年もかかるんでしょう?そのあいだは低収入になるんですよね?
- 補助金って頼るとよくないんでしょ?
- 有機農業のほうがいいの?
- どの作物が儲かるの?
- 観光農園って儲かるんですか?
- 6次産業化ってよく聞くけど、やったほうがいいんですか?
- オランダみたいに日本も農産物輸出大国を目指すべきだと思うですが、どうですか?
- AI、IOT、ロボットを投入すれば農業を革新できるのでは?
- 農家になったら「24時間365日」心血を注がないとダメですか?
- で、結局、何を入り口にしたらいいですか?
- 農業をはじめるための6つのステップ
- モデルケースを見てみよう〜就農2年目・國中秀樹さんの場合〜
- まとめ 10年間の経営計画表の書き方
- 『絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業』を読んで今後勉強すべきこと
- まとめ
『絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:岩佐大輝
- 出版社:朝日新聞出版
- 発売日:2018/3/20
- ページ数:216ページ
【目次】
第1部 農業についてのよくある疑問と不安
- 農業って儲かるの?
- 作物を作ったのに、売れなかったらどうするの?
- 天候が原因で不作になったら、借金まみれになるのでは?
- 農協ってよく批判されているけど、使わないほうがいいの?
- 都会出身の人間が地方に移住してやっていけるもなの?
- 農地を借りる、買うのはやっぱり大変?
- やっぱり修業に何年もかかるんでしょう?そのあいだは低収入になるんですよね?
- 補助金って頼るとよくないんでしょ?
- 有機農業のほうがいいの?
- どの作物が儲かるの?
- 観光農園って儲かるんですか?
- 6次産業化ってよく聞くけど、やったほうがいいんですか?
- オランダみたいに日本も農産物輸出大国を目指すべきだと思うですが、どうですか?
- AI、IOT、ロボットを投入すれば農業を革新できるのでは?
- 農家になったら「24時間365日」心血を注がないとダメですか?
- で、結局、何を入り口にしたらいいですか?
第2部 農業をはじめるための6つのステップ
- ステップ1 農業をやる目的を言葉にする
- ステップ2 自分が望む生活スタイル(収入、時間の使い方)を決める
- ステップ3 作物・作型(育て方、こだわり)を考える
- ステップ4 10年間の経営のビジネスプランを数字に落とし込む
- ステップ5 資金調達の方法
- ステップ6 情報収集とネットワーク作り
第3部 モデルケースを見てみよう〜就農2年目・國中秀樹さんの場合〜
まとめ 10年間の経営計画表の書き方
絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業は、「土地なし、ノウハウなし、資金なし」でも、年収を落とさずに農業をはじめるための新規就農本です。
著者は、株式会社GRA代表取締役CEOで、「IT×農業」でイチゴビジネスに構造変革を起こし、ひと粒1000円の「ミガキイチゴ」を生み出しています。
数々の章も受賞しています。
- 「ジャパンベンチャーアワード」(中小機構主催)「東日本大震災復興賞」(2014年)
- 「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」(内閣府後援)「地方創生賞」(2015年)
新規就農支援事業にも精力的に取り組んでいます。
『絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業』を読んで勉強になったこと
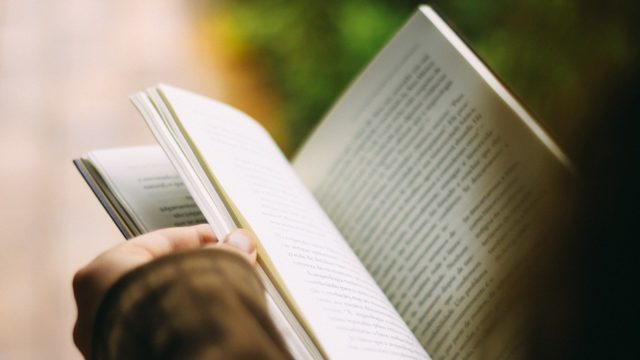
農業において唯一の成功とは地に足をつけて「続ける」ことだと定義しています。
農業には中長期的なビジョンが不可欠で、瞬間的に稼げてもそれだけでは成功とは言えません。
いかにして続けていくかについて、本書内にて記載されています。
各項ごとで勉強になったことについてまとめさせていただきます。
農業って儲かるの?
農家の「見かけの所得の低さ」に騙されてはいけません。
販売農家は農業所得以外の所得がありますが、農業所得のみを見ると平均所得より低く、儲けられていないように感じます。
しかし、農家は個人事業主・中小企業であり、経費で所得を圧縮すること、税金を減らすように所得を小さく見せようとします。
実際に収益シミュレーションを実施して、儲かるのか検討する必要があると著者はしています。
作物を作ったのに、売れなかったらどうするの?
農作物をせっかく作ったのに全然売れない場合はありません。
農業に関しては、市場は作ったものを受け取って売る「引き受け業務」が「卸売市場法」という法律で決められています。
どの作物が市場平均いくらで売買されているのかは農林水産省HPの「青果卸売市場調査」で品目別に調べることができ、作付面積と品目が決まれば売上の予測もできます。
市場価格の変動があり、直販・契約栽培がもてはやされることがありますが、一長一短があることを理解しなければなりません。
市場を使えば、売りなくて困ることはないが、価格決定権がない。
直販を使えば、価格決定権があるが、販路の開拓が難しい・他の農家の安売りによる値崩れなどがあります。
契約栽培を使えば、価格はあらかじめ決まり安定しているが、出荷数量・時期を厳守しなければなりません。
天候が原因で不作になったら、借金まみれになるのでは?
全国的な不作であれば、需要と供給のバランスにより、生産量が減っても価格が上がるので、意外になんとかなります。
しかし、自分の産地だけ局地的気象原因で不作が生じると、売上が激減してしまいます。
天候リスクに対しては、頑丈なハウスを建て、災害保険・共済に入ることで備えることができますが、コストがかかります。
逆にこれらの初期投資をしない代わりに、借金を抱えずに天候リスクを引き受けることを選択することができます。
農協ってよく批判されているけど、使わないほうがいいの?
農業をやっていないと「農協=悪」のような印象がありますが、農村部においては異なります。
農協を通して市場に卸すと、個人でやるよりも高い単価になることが多いです。
それは農協が産地としての信頼・品質を担保し、一定以上のロットを安定して市場に供給することができるからです。
そのため、著者は良い農協を以下のように表現しています。
個人が荷受会社に出すよりも農協を通したほうが高く値が付き、農協に手数料を払ってもそれ以上に利益があるところは、良い農協と言えます。
引用:『絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業』p36 5〜7項
良い農協ほど、品質を確保するために閉鎖的・排他的ではあり、手数料も取られます。
それを嫌がる人もいますが、農協のシステム・販路を自分で用意することができませんので、仕方のないことです。
都会出身の人間が地方に移住してやっていけるもなの?
作りたいものがあるなら、その産地を選ぶことがまず大事です。
そして、血縁・地縁のない土地で農地を買う・借りるにはノウハウが必要です。
まず、市町村の農政課に行って、農業委員を紹介してもらい、話を聞いてみることを著者は勧めています。
農地を借りる、買うのはやっぱり大変?
新規就農者が最も苦労するのが「農地の確保」で、土地が用意できずに就農できないことは少なくないようです。
耕作放棄地がたくさんある一方、良い土地は取り合いが起きています。
そのため、土地のキーマンと仲良くなるために、コネができそうなスクール・コミュニティ・農業法人などに所属する必要があります・
やっぱり修業に何年もかかるんでしょう?そのあいだは低収入になるんですよね?
農業は、株植えから収穫までの1サイクルがとても長期間有します。
農業教育は経験主義・現場主義であり、一人前になるためにさらに長期間必要なことは必須です。
そのため、ノウハウを持っている人・集団に教わり、1人で学んでいたら10年かかるものを1年に短縮することができます。
補助金って頼るとよくないんでしょ?
補助金漬けの農家は良くないというイメージがありますが、著者は取れる補助金を全て取ったほうがいいと説明します。
資金調達のチャンスであり、銀行の借入・株式発行による調達と同じです。
補助金には、認定新規就農者になる必要があるなど要件はありますが、事前に確認・把握しておいたほうが良いです。
有機農業のほうがいいの?
そもそもなぜ有機でやりたいのかを定める必要があります。
単位面積あたり・労働工数あたりの生産量が減るため、単価を上げないと採算が取れないため、有機で儲かるには販路確保が大事になります。
どの作物が儲かるの?
市場原理が働き、作るのが大変な作物の単価は安く、作るのが簡単な作物の単価は高くなります。
そのため、作業時間あたりの売上単価はどの農作物を選んでも劇的に変わりません。
規模の経済が効く作物(固定費型)の場合は、大規模な投資をして大量に作ると投資効率が良くなるので、たくさんお金を投じられる大企業に有利です。
逆に規模の経済が効かない作物(変動費型)の場合は、いくら投資しようが作物を作るコストはそれほど変わらないので、小規模農家でも不利になりにくいです。
初期投資が少なくて済むものは競争相手が多くなってしまいますので、初期投資がかからない作物にしようと安易に考えるのは危ないです。
リスクとリターンのバランスが取れているので、一概にどの作物・作型が儲かるとはいえないです。
観光農園って儲かるんですか?
「摘み取って、パッキングして、売る」という出荷に関わるコスト(手前、人件費)が大きい労働集約型の作物の場合は、観光農園をやるメリットがあります。
ただし、摘み取りコスト(変動費)を削減できますが、代わりに観光農園の宣伝費・スタッフなどの固定費が必要になります。
変動費型から固定費型に作物型をシフトしたい場合に、観光農園はおすすめです。
また、最終消費者と触れ合うのが楽しいと思う人にも向いています。
しかし、しっかりと作物が作れるようにならないとお客さんは満足しませんので、観光農園をやるなら安定して作物が作れるようになってからにしましょう。
6次産業化ってよく聞くけど、やったほうがいいんですか?
著者は、安易な6次産業化を勧めていません。
加工食品を作成した場合、競争相手が農家から大手食品メーカーになります。
コスト面で調達できないもの・大手がそもそも入手できないもので戦い、地域密着性で戦うしかありません。
オランダみたいに日本も農産物輸出大国を目指すべきだと思うですが、どうですか?
農産物を輸出する場合近隣のASEANを考える場合が多いですが、ごく一部しか市場シェアしか取れていません。
それは、輸出用の育種戦略をとっておらず、製造原価を抑えて価格競争で勝てる工夫もしていないからです。
国と国とのデリケートな関係性によって左右される点もあり、国内ビジネス以上に難しいです。
AI、IOT、ロボットを投入すれば農業を革新できるのでは?
AI・IOT・ロボットは、問題を解決に貢献するかが重要です。
技術が新しいかどうかということは関係ありません。
テクノロジーを使えばうまくいくものではありません。
農家になったら「24時間365日」心血を注がないとダメですか?
農業でも他の仕事と同様に急なトラブルが発生することがあります。
しかし、24時間365日働かないといけないなら、設備・仕事の進め方に根本的な問題があります。
そんな状態では高齢者ばかりの従業員は雇えないし、労働強度を下げて、労働時間を設定しなければなりません。
で、結局、何を入り口にしたらいいですか?
まず、収納のきっかけとして農業体験をすることを著者は勧めています。
時間とお金があるなら農業大学校も勧めています。
農業をはじめるための6つのステップ
著者が、農業を始めるための手順を6つのステップで説明しています。
- ステップ1 農業をやる目的を言葉にする
- ステップ2 自分が望む生活スタイル(収入、時間の使い方)を決める
- ステップ3 作物・作型(育て方、こだわり)を考える
- ステップ4 10年間の経営のビジネスプランを数字に落とし込む
- ステップ5 資金調達の方法
- ステップ6 情報収集とネットワーク作り
ステップ1 農業をやる目的を言葉にする
そもそもなぜ農業をやりたいのかをはっきりと言語化しておく必要があります。
ステップ2 自分が望む生活スタイル(収入、時間の使い方)を決める
自分がどのようなライフスタイルを送りたいのか決めるため、農業の以下の面を考慮します。
- 働く季節
- 労働時間
- 手取り収入
ステップ3 作物・作型(育て方、こだわり)を考える
農業をやる目的・ライフスタイルが定まったところで、それに適した作物・作型選びを行います。
いくつかの選び方のパターンが挙げられています。
- 農業をやる目的から考える
- 好きなものを作る
- 理想の生活から考える
- 売上がブレないことを重視する
上記は内部環境をもとに考えていますが、以下の外部環境にも注意をしながら選択するべきだと記載されています。
- 消費量が少ない作物は難易度が高い
- 「作るのが簡単で単価が高い=新規就農者におすすめ」ではない
- 将来的に市場が激減しそうなものは避けよう
- 輸入の脅威が大きいもの、政府の方針に左右されるものも難易度が高い
- 日本人全体のライフスタイルの変化も考えよう
- 数字の向こう側にある、人間の心理を見る
- 世界全体の中での動向も見てみよう
- 作りたいものがあるなら、妥協で他の作物を選ぶべきではない
- 多品目をうまくやるための考え方
ステップ4 10年間の経営のビジネスプランを数字に落とし込む
農業は設備投資した資金の投資回収までに10年前後かかるため、著者は10年間のビジネスプランにそれらの数字を落とし込む必要があると言います。
トラクターやビニールハウスの減価償却に5〜10年かかるのが一般的です。
10年間のビジネスプランの作成手順が記載されています。
- 手順1 売上:売上=出荷量×市場平均価格(初年度は平均の60%で5年後平均並で計算)
- 手順2 初期投資:売り上げに対する減価償却費を15〜20%に抑える
- 手順3 維持費用・継続費用:コストから固定費型・変動費型かを判別
他にも考えるべきことが詳細に記載されていました。
ステップ5 資金調達の方法
資金調達は主に「補助金・銀行からの借入・株式発行」になります。
銀行は事業の継続性、投資家は事業の成長性を見ます。
ステップ6 情報収集とネットワーク作り
農家が単独でデータを採取しても、10年で10個しかデータは蓄積されません。
近所農家と協力し、地域全体で価値を共に創っていくことが農家には求められます。
品種などの知的財産を保護しながら、周囲からの協力を得ていく努力が大事になります。
モデルケースを見てみよう〜就農2年目・國中秀樹さんの場合〜
上記の6ステップをどのように実施したのかという事例が載っています。
就農2年目・國中秀樹さんは施設園芸単一品目・露地野菜多品目を実施しています。
新規就農者のリアルな体験談が記載されており、大変参考になりました。
まとめ 10年間の経営計画表の書き方
最後に10年間の経営計画のひな型が用意されています。
実際に経営計画表を作ることで、『絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業』の内容の復習もできます。
『絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業』を読んで今後勉強すべきこと

『絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業』を読んで、経営計画書の重要性について理解することができましたので、経営計画書についてもっと勉強したいと思いました。
そこで、経営計画に重きを置かれた就農本である『就農は「経営計画」で9割決まる 農業に転職!』を読んでみます。
また、『絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業』の中で観光農園が変動費型から固定費型に作物型をシフトしたい場合におすすめされていました。
そこで、観光農園での農業起業を成功し、観光農園をおすすめしている『最強の農起業!』を読んでみます。
まとめ
『絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんが、感想・内容を紹介しました。
まだまだ勉強不足ですので、これらからもしっかり勉強していきます。
最新の農業情報を得るためには、本だと出版までのタイムラグがあるので、農業の専門雑誌を読むほうがおすすめです。
毎月購入すると結構コストがかかってしまうので、ネットで農業雑誌・家庭菜園誌が読み放の「楽天マガジン」がおすすめですので、利用してみてください。