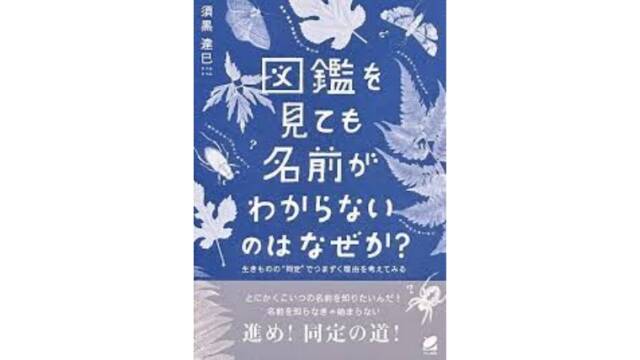自然・野生生物を観察する際に、写真を撮ることもありますが、なかなか上手に写真が撮れません。
そこで、少しでも上手く撮るために勉強をしようと思って、『動物を撮る!「写真の学校」』を読んでみました。
とても勉強になりましたので、書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんが紹介します。
目次
『動物を撮る!「写真の学校」』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:
- 出版社:雷鳥社
- 発売日:2009/10/1
- ページ数:235ページ
【目次】
- プロローグ
- 1.動物撮影とは
- 2.動物撮影の基礎知識
- 3.身近な動物を撮る
- 4.フィールド撮影にチャレンジ
『動物を撮る!「写真の学校」』は、フリーの動物写真家である著者の前川貴行氏が、写真を撮るためのエッセンスを詰め込んだ1冊です。
カメラ機材・撮影テクニック・装備・フィールドのアクセスなど、多岐にわたる内容がまとめられています。
等身大な現場の雰囲気が伝わる内容に加えて、昆虫写真家「新開 孝」・水中写真家「白鳥 岳朋」のインタビューもあります。
『動物を撮る!「写真の学校」』を読んで勉強になったこと
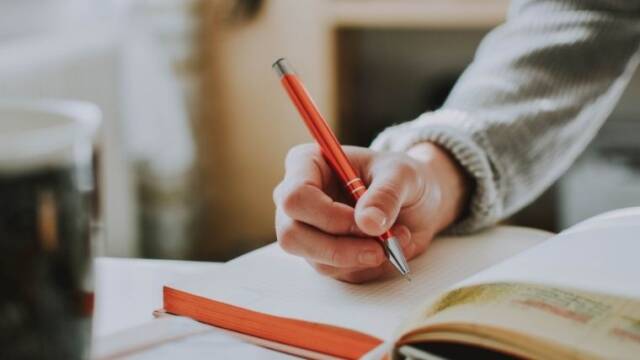
動物を撮る!「写真の学校」では、動物写真を撮るための知識が得られる1冊です。
情報が多岐に渡るため、章ごとに重要だと思ったことをまとめます。
1.動物撮影とは
この章では、動物写真を撮る前の心構えが記載されています。
動物の撮影をする上で大切なことは、被写体となる動物についてできる限り調べることです。
【調べるべき基礎項目】
- 国と地域
- 活動する季節
- 生息環境
- 食べ物
- 特徴や習性
2.動物撮影の基礎知識
この章では動物撮影の基礎知識として、
- 機材とアクセサリーの準備
- 撮影の準備
- 被写体を選ぶ
- 撮影テクニックによる表現の違い
が記載されています。
機材とアクセサリーの準備
動物撮影で必要となる機材として、以下のものが挙げられています。
- カメラ:デジタル一眼カメラ・フィルム一眼カメラ・コンパクトデジタルカメラ
- 記録メディア:RAWデータ1カット10〜30MBなら16GB・32GBのメモリー
- レンズ:レンズを多くすれば行動力が落ちるので、使いたいレンズと自分の体力との兼ね合いで決める
- ストロボ:カメラに内蔵されていても、外付けのクリップオンタイプを1つは用意
- 三脚:一番重いレンズを支えられ、軽量なものを選ぶ
- 雲台:超望遠用を用意
- カメラザック:軽量タイプのものを選ぶ
撮影の準備
撮影をする前に撮影機材について理解が必要です。
- レンズワーク:焦点距離の違いによる効果、フォーカスの使い分けなど
- スローシンクロ:早朝・夕暮れで、スローシャッターで背景に露出を合わせ、ストロボで被写体を浮かび上がらせる
- 日中シンクロ:日中で逆光・反逆光時にストロボを使って被写体が暗くなるのを防ぐ
- デジタルワークフロー:画像劣化しづらく現像処理しやすいRAWデータで撮影し、撮影から戻ったらハードディスクに全てコピーする
- レタッチとプリント:自分の意図する色味やコントラストに仕上げて、校正設定で実際に色味を確認してからプリントする
被写体を選ぶ
以下の被写体から撮影する動物を選びます。
- ペット
- 動物園の動物
- 野鳥
- 野生動物
撮影テクニックによる表現の違い
表現の幅が広がるテクニックが紹介されています。
- 被写体の動きを止める:1/500以上のハイスピードシャッターを使う
- 躍動感を出す:止まっている部分とブレている部分を共存させる
- シルエットで撮る:逆光で背景の雰囲気を使う
- 流し撮り:ゆっくりとカメラを振って、背景を流す
3.身近な動物を撮る
この章では身近な動物の撮り方として、
- ペットを上手に撮る
- ピントとフレーミング
- 動物園で撮る
が記載されています。
ペットを上手に撮る
ペット撮影の良いところは、自分の好きな場所で撮影できる点です。
背景は、基本的には極力シンプルになるように心がけ、主役であるペットが浮き上がるようにごちゃごちゃした要素を外して、抜けのいい写真を目指します。
活き活きとした姿を捉えるには、以下の方法を用います。
- 声をかけながら撮る
- 瞳のキャッチライトを意識する
- 動きを積極的に撮る
- アシスタントを頼む
ピントとフレーミング
瞳には生命力が如実に表れるので、動物の場合は基本的に瞳にピントを合わせます。
フレーミングは、被写体が最大限に引き立つように背景を考え、余分なものはフレームから取り除きます。
動物園で撮る
動物園での撮影について、雑誌・書籍などの仕事が絡む場合は園に撮影許可の申請を行う必要があります。
営利目的ではなければ、園内での撮影許可を求める必要はありません。
柵内に入ったり、フラッシュ禁止区間で発行させないなど、一般客と同様のルールを守りさえすれば大丈夫だが、三脚を広げての長時間撮影は控えましょう。
野生と違い、季節・天候・時間帯・旬な時期を狙って動物園に行くことできます。
動物園での撮影で大きな障害になるのは、柵・檻の存在です。
柵・檻越しに撮影するには、フードを外して、レンズを傷つけないようにレンズ前面をピタリとくっつけ、棒と棒のちょうど真ん中にレンズの中心が来るようにします。
ガラス面にくっつけて撮影をすると、ガラスの写り込みを防ぐ効果もあります。
4.フィールド撮影にチャレンジ
この章ではフィールド撮影のための知識として、
- フィールド撮影への準備
- 野鳥を撮る
- 野生動物を撮る
- 夜間撮影のテクニック
が記載されています。
フィールド撮影への準備
フィールド撮影に必要な装備について以下のものが挙げられています。
- フィールドウェア:寒暖・風雨・岩擦など耐久性があるもの
- フィールドギア:多機能ナイフ・双眼鏡・フラッシュライト・ドライタオル・サングラス・ペッパースプレー・ザイル・ハーネス・ソーラーパネル(バッテリー)
- カメラのケア用品:レインカバー・乾燥剤・防虫剤・クリーニングペーパー・ブロア
野鳥を撮る
野鳥を撮るなら、500mm以上の超望遠レンズが必要がなります。
フィールドスコープとコンパクトデジカメを組み合わせて、気軽に1000〜2000mmの超望遠レンズが作れる「デジスコ」ができます。
機材を揃えても、被写体に接近しなければ満足のいく大きさで写すのは難しいです。
野鳥への接近しては逃げられを繰り返して、アプローチの仕方を学ぶしかありません。
野鳥を撮るシチュエーションとして、「飛翔・ペア・群れ・習性・獲物を食べる・営巣」などがあります。
野生動物を撮る
撮影場所までのアプローチの手段によって、撮影方法や日程によって大きく変わってきます。
野生動物の撮影における醍醐味は、現場近くでキャンプしながらの撮影です。
何日間も、何週間も自然の中で寝起きして動物と対峙するのは、貴重な体験です。
夜間撮影のテクニック
夜間撮影は、センサーを使用した無人撮影が一般的です。
明るいうちに動物が来てそうなところにカメラ・センサーでセットし、数日後に回収しに行くやり方です。
無人撮影は何が撮れているか分からないのですが、ファインダーを覗きながら撮影することも勧めています。
『動物を撮る!「写真の学校」』を読んで今後勉強すべきこと

『動物を撮る!「写真の学校」』を読んで、もっと写真について勉強しなくてはいけないなと感じました。
同じような動物の撮り方を学ぶ本として、natureが出版している『動物撮影の教科書』を読んでみます。
また、野鳥の撮り方が図解されている『図解でわかる野鳥撮影入門』も読んでみたいと思います。
まとめ
『動物を撮る!「写真の学校」』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんが紹介しました。
写真を上手に撮るためには、まだまだトレーニングが必要ではありますが、少しずつ実践していこうと思います。