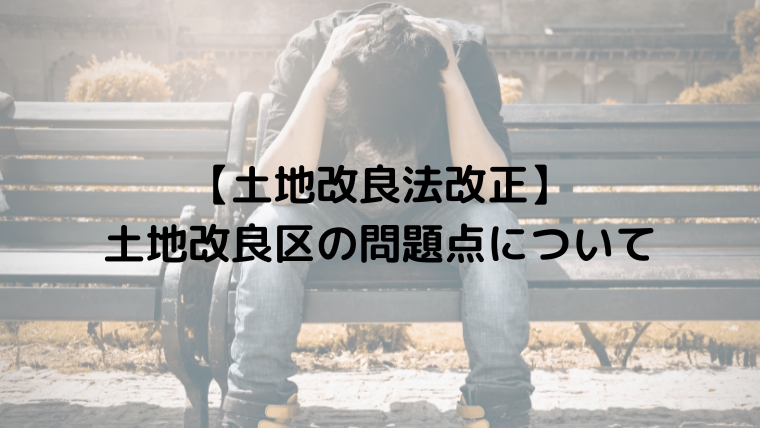平成29年度から土地改良法の改正が行われ、「土地改良区の運営」に関して改正があった。
農業の担い手不足が深刻化しており、土地改良区の組合員は減少傾向にあります。
土地改良区に求められる役割が多面的に広がっており、「辞めたい」「いらない」などの多くの問題が噴出しており、良い改正とは言えないかもしれません。
早急な対応が求められる中懸念事項が多く挙げられ始めたので、まとめてみました。
【土地改良法改正で生じる土地改良区の問題点について】
- 問題点①利水調整のルール化
- 問題点②複式簿記の義務化
- 問題点③準組合員制度の導入
- 問題点④総代会制度の導入
- 問題点⑤員外監事の導入
問題点①利水調整のルール化

法改正により、総会の議決をもって利水調整規程を定める必要があります。
国の規定例を参考に作成すると、利水調整のルール作成は時間的・技術的に困難です。特に、複数の水路系統があったり、水路の上下流で複数の土地改良区と調整が必要である場合、さらにルール作成は困難になります。
しかし、これら複雑なルール作成により、干天時や増水時などの天災時に柔軟な対応が出来ないことが想定されます。詳細なルール化に加えて、様々な状態に対応できるルール作成が求められます。
これらは、法改正により利水系統ごとに土地改良区連合を設立できるようになってことを推進する意味合いもあります。
問題点②複式簿記の義務化

土地改良区の財務会計制度は、単式簿記で行われることがほとんどでしたが、複式簿記にて行うことが義務化されました。
この複式簿記では、賃借対照表を作成して、土地改良施設の資産評価が必要になります。土地改良資産の資産評価はとても難しく、国のマニュアル化、県・市町村・土地改良区連合等との協力体制が重要になります。
複式簿記を取り入れて自団体では厳しい場合は、税理士に丸投げするしかありません。
少しでも顧問料を減らしたいなら、相見積りができる税理士ドットコムなどで探して見てください。
問題点③準組合員制度の導入

改正により、準組合員制度が導入され、貸借地の所有者か耕作者で事業参加資格がないものを准組合員とすることができます。
准組合員は、議決権や選挙権を有しないが、総会に出席して意見を述べることができ、組合員との間で賦課金・夫役の一部を分割負担することができます
また、地域住民を構成員とする団体を施設管理准組合員とすることができます。施設管理准組合員は、議決権や選挙権を有しないが、総会に出席して意見を述べることができ、土地改良施設の管理への協力を求めることができます。
準組合員制度は、賦課金を準組合員を通して地域で負担していくメリットがあります。また、農村に重要な施設管理に対する希薄化への対策にもなり、耕作者が主体であった土地改良区で、地主等が参画する機会を与えます。
しかし、以下のような事務が増えます。
- 加入・脱退手続き
- 名簿管理
- 総代会の出席要請
- 意見陳述手続き
職員が0~1人である小規模な土地改良区において、このような事務量の増加は負担が大きいです。
問題点④総代会制度の導入

総代会制度の見直しにより、組合数100~200人の土地改良区は、新たに総代会を設置することを検討する必要があります。
総代会設置により、選挙管理委員会による管理の廃止・書面や代理人での議決権の行使などのメリットがあります。
しかし、このような規模の土地改良区は、職員が0人である場合がほとんどであり、適切な総代会運営が厳しいとの声があります。
「辞めたい」「いらない」という声も噴出する理由がよくわかります。
また、総代会による簡易な意思決定により、土地改良区に対する関心の低下を引き起こすのではないかとの声もあります。
問題点⑤員外監事の導入

監事のうち員外監事を1人以上選任する必要があります。
例外として、外部監査を受けることで免除できます。しかし、監査を受けるためには、人材的・費用的に負担がかかるため、外部監査を受けることを選択することは難しいです。
員外監事を選任を検討する場合、員外監事が建前的なものにならないように指導する必要があります。
まとめ

土地改良法改正の問題点についてまとめさせていただきました。
「のうぎょうとぼく」の中では、農業土木に関する豊富な記事を書いています。
農業土木について勉強できる本については下記にてまとめていますので、ぜひご覧ください。
参考ページ:農業土木の勉強におすすめな参考書・問題集を紹介!