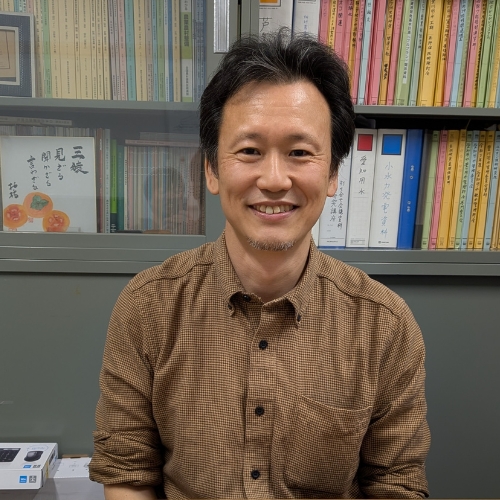「のうぎょうとぼく」では、農業土木の重要性・魅力を若い世代に伝えていく活動をしています。
その一環の1つで、農業土木の専門家である研究者・技術者にお話を伺い、WEB記事という形で情報発信をしております。
今回は、私の母校である岐阜大学応用生物科学部で、土や水の魅力を絵本という形で表現する珍しい試みをされた「大西健夫教授」に取材させていただきました。
目次
岐阜大学応用生物科学部について
岐阜大学応用生物科学部は、生命科学や生物環境科学を基盤とした教育と研究を行い、食品・環境・健康・生物産業などの分野で活躍できる人材を育成する学部です。
実験やフィールドワークを重視したカリキュラムで実践的な学びができます。
令和7年4月に学科の再編がありし、4学科体制になりました。。
- 応用生命化学科
- 食農生命科学科
- 生物圏環境学科
- 共同獣医学科
生物圏環境学科の中で、農業土木を学ぶことができます。
生物圏環境学科
生物圏環境学科は、水・物質循環、生態系管理、動物保全を融合させた学科です。
岐阜大学キャンパス内の附属農場・美濃加茂農場・位山演習林などのフィールドを活用した実践的な実習や実験を行います。
- 主な授業科目:生物圏環境学の実践的実習とデータサイエンス、水・物質循環・生態系を理解する科学、動物の生息域内・域外保全、生物多様性保全と生態系管理技術
- 卒業後の進路:農業土木/環境コンサルタント・緑化造園業・動物園/水族館・農林水産省等の技術職
参照:岐阜大学応用生物科学部「デジタルパンフレット」より
大西健夫教授について
- 所属:岐阜大学 応用生物科学部 流域管理学研究室 教授
- 学位:博士(2004年3月 京都大学)
- J-GLOBAL ID:200901094799494186
- researchmap会員ID:1000258818
- 基本情報:水文学的手法にもとづく, 流域の水・物質( 窒素, リン, 炭素,鉄など) 循環研究.
森川海のつながりの中での農林水産業という視点を重視しています。
参照ページ
・researchmap「大西 健夫」
・国際農環境科学研究室
インタビュー内容

大西健夫教授が携わった『水のはなし』『土のはなし』を中心に据え、農業土木についてお話させていただきました。
『水のはなし』は令和2年度水文・水資源学会「学術出版賞」、『土のはなし』は、第33回読書感想画中央コンクールで低学年の部の指定図書に選定され、2022年度農業農村工学会賞「著作賞」を受賞しています。
約1時間半インタビューした内容を、ぎゅっとまとめました。
【大西健夫教授へのインタビュー内容】
- 絵本制作のきっかけ
- 1冊目『水のはなし』について
- 2冊目『土のはなし』について
- 絵本と農業土木の繋がり
- 今後のアウトリーチ・研究について
絵本制作のきっかけ
1冊目『水のはなし』について
2冊目『土のはなし』について
絵本と農業土木の繋がり
今後のアウトリーチ・研究について
まとめ

岐阜大学応用生物科学部の大西健夫教授にお話を伺いました。
ご協力頂いた先生方・広報関係の皆様による多大なご尽力によって取材をさせていただきましたこと、厚く感謝申し上げます。
少しでも多くのコンテンツを作成し、農業土木を学ぶきっかけづくりをしていければと思います。
農業土木の一端に触れるきっかけとして、『水のはなし』『土のはなし』をぜひ読んでみてください。