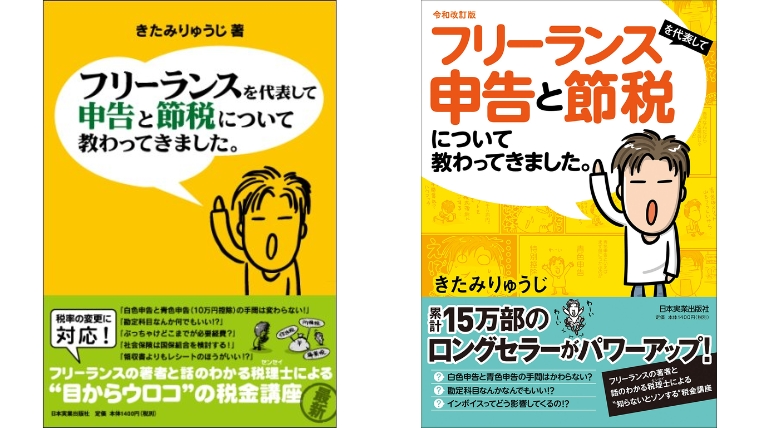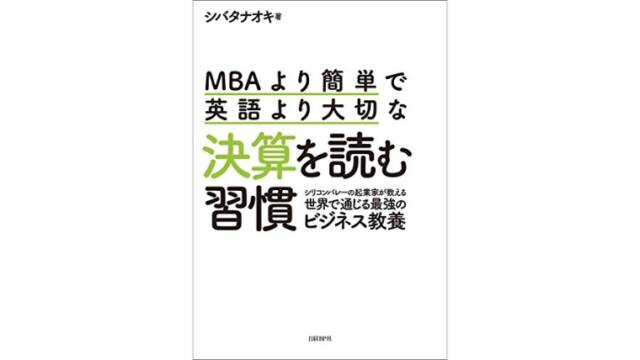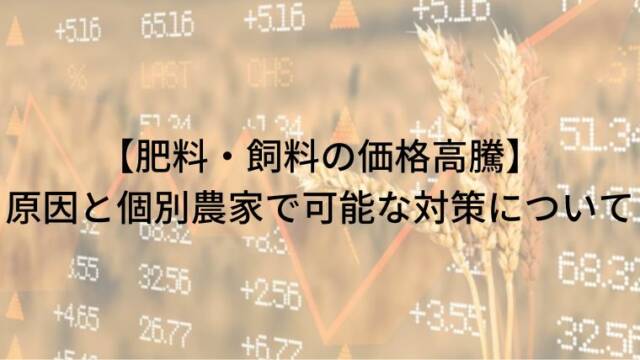農家として生きていくことは、農業を生業として起業するということです。
農産物を生産することばかりに気を取られて、経理などの経営面が疎かになってしまいます。
そのため、経営・節税について勉強することは農家には必要です。
その一環として『フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。』を読みましたので、書評・要約のように綺麗に整理できていませんが、感想・勉強になった内容をまとめてみます
目次
『フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:
- 出版社:日本実業出版社
- 発売日:2005/12/8
- ページ数:232ページ
【目次】
- 第1章 税金ってなんぞや?
- 第2章 カシコクいこう社会保険
- 第3章 記帳業務はシゴトの家計簿
- 第4章 ムダなく納税の青色申告
- 第5章 知らずにすまない消費税
- 第6章 いずれは見すえる法人化
- 第7章 しのびよる税務調査の影
『フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。』は、フリーランスのライター兼イラストレーターである著者のきたみりゅうじ氏が税理士から「申告と節税」の講義をうけて、理解する過程をわかりやすくまとめた1冊です。
著者自身の体験に基づいて話を聞いているため、フリーランスの人が抱きやすい疑問や誤解についても解決してくれます。
多数のイラスト・4コマ漫画で、申告・節税の知識を楽しんで身につけることができます。
令和版も発売されており、最新の情報を盛り込んでいます。
『フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。』を読んで勉強になったこと

『フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。』では、フリーランスに必要な税の知識を、4コマ・イラストを通して学ぶことができます。
特別な知識というよりは、税の基礎知識をしっかり学ぶことができます。
章ごとに重要だと思った内容をまとめさせていただきます。
第1章 税金ってなんぞや?
【第1章の小見出し】
- 一応おさえる税金の歴史
- 税金は引き算とかけ算できまるのだ
- 申告納税の基礎
- 給与所得を知らずして控除の道はならず
- 税金は安けりゃいいってもんじゃない
- いろいろあるぞ税の種類
日本の税制が所得税中心であり、超過累進課税制度であることが取り上げられています。
サラリーマンなどの給与所得者は年末調整がされますが、フリーランスなどの事業所得者は年末調整がされないため確定申告が必要です。
納付税額=課税所得(所得(売上ー経費)ー各種控除)×所得税率
本書の題名に「節税」と書いてありますが、著者はしっかり「税金は安けりゃいいってもんじゃない」と説明しています。
経費や控除で所得を小さくして納付税額を抑えすぎると、所得が少ないことで
- 事故などで補償を受けるとき、補償額が少なく
- ローンが組めなくなる
などの問題点があります。
税金について、所得税・住民税・事業税・固定資産税・消費税などについても記載されています。
その中でも、事業税は課税対象事業を営んでいる人が収める税金で、著者はライターなので文筆業として課税対象事業外で課税されないことが記載されています。
第2章 カシコクいこう社会保険
【第2章の小見出し】
- 社会保険の種類
- 健康保険の基礎知識
- 年金の基礎知識
- 社会保険と税金の関係
フリーランスなどの自営業者が加入する「国民健康保険」についても記載されています。
国民健康保険は、世帯単位で加入するもので、世帯全員の年間収入で保健料が算出されます。
国民健康保険以外にも、職能団体などで運営される国保組合というものがあり、加入条件などはありますが割安で定額な場合があります。
年金は、国民年金に加えて国民年金基金・小規模企業共済を上乗せすることができ、控除に計上することができます。
第3章 記帳業務はシゴトの家計簿
【第3章の小見出し】
- 記帳ってなんじゃいな
- 領収書は額面10%の金券なのだ
- レシートってどうなのさ
- 領収書がない場合
- ぶっちゃけどこまでが必要経費?
- デキた勘定科目は七難隠す
- 固定資産と減価償却
- 損益計算書(収支内訳書)でいっちょあがり
経費を計上するために、領収書を添付する必要があり、金券のように大事なものであると説明しています。
支払いの照明ができればレシートであっても大丈夫で、これらがない祝儀などの場合は伝票処理をします。
どこまでが経費であるかという点において、少しブラックな感じで、「安全じゃなくてもかまわないなら、仕事に関係するものを片っ端からのっけていけばいい」というスタイルです。
経費の勘定項目については、ある項目だけが突出して目立つ金額になるのを避けた方がいい、毎年毎年項目がコロコロ変わるのは望ましくない、などのアドバイスがされています。
第4章 ムダなく納税の青色申告
【第4章の小見出し】
- 青のはじまりは申請から
- 記帳水準でかわる控除額
- 他にどんなメリットが?
- 賃借対照表と事業主貸・事業主借
- 青色専従者給与はメリットいっぱい
- 減価償却の特例も見逃せない
- 損失は繰り越せるのだ
- 青色申告会ってナニよ?
青色申告ができるように、一から説明がされています。
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色申告特別控除額
- 青色専従者給与
- 少額減価償却資産
- 純損失の繰越控除
節税効果の高い「青色専従者給与」については、特に重要だと思いました。
同一家計の配偶者等に支払った給与を経費にすることができるため、従業員に準ずるレベルの報酬を支払うことができるので、大きく節税をすることができます。
第5章 知らずにすまない消費税
【第5章の小見出し】
- 1千万円を境目に納税義務はやってくる
- 課税取引と非課税取引
- 消費税額の計算方法
- フリーランスは簡易課税でじゅうぶんだ
前々年の売上が1000万円以下であれば、免税事業者であり、消費税が免除されています。
仮に1000万円を超えてしまっても、5000万円未満で申請書を出せば、「簡易課税制度」を使えます。
事業の種類に応じた「みなし仕入れ率」を用いて簡単に消費税が計算できます。
第6章 いずれは見すえる法人化
【第6章の小見出し】
- なんで法人化するの?
- 株式会社と有限会社
- 法人ってナニがいいのよ?
- んで、結局どうなったら法人化するの?
法人化のメリットとして、自分に給与を支払うことで、給与控除などの節税効果・社会信用の増加が挙げられています。
逆にデメリットとして、法人税住民税・税務調査が入りやすいなどが挙げられています。
700〜800万円をコンスタントに稼げるようになれば、法人化にすると良いかもしれないので、税理士に相談してみると良いそうです。
第7章 しのびよる税務調査の影
【第7章の小見出し】
- 調査はある朝突然に
- 調査は実際のとこどんな感じ?
- 税務調査の後始末いろいろ
- 対策には何がある
税務調査は、個人1%・法人6%ほどの確率で当たります。
税務調査で問題になるのは、光熱費や車などの按分比率です。
これについて、修正申告をした場合、追加で支払う税金に対して「過少申告加算税・延滞税」がかかります。
これらは追加の税金の三割程度になるので、ガンガン経費に乗っけてしまっても大丈夫だと説明しています。
『フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。』を読んで今後勉強すべきこと

『フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。』で、税金の申告と節税について、少し理解することができたと思います。
法人化した場合の節税方法も勉強しようと思うと、別の本での勉強が必要になります。
社員を抱えない小規模法人なら「日本一わかりやすい ひとり社長の節税」が良いかもしれません。
社員やパートを雇っていくなら、「小さな会社が本当に使える節税の本」良いでしょう。
まとめ
『フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。』を読むことで、フリーランスの申告と税金について、少し触れることができたと思います。
起業をしていくためには、まだまだ知識が必要ではありますが、少しずつ実践していこうと思います。
より優れた農業をいと舐めるように、色々な本を読んでみたいと思います。